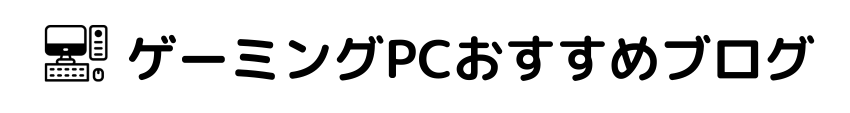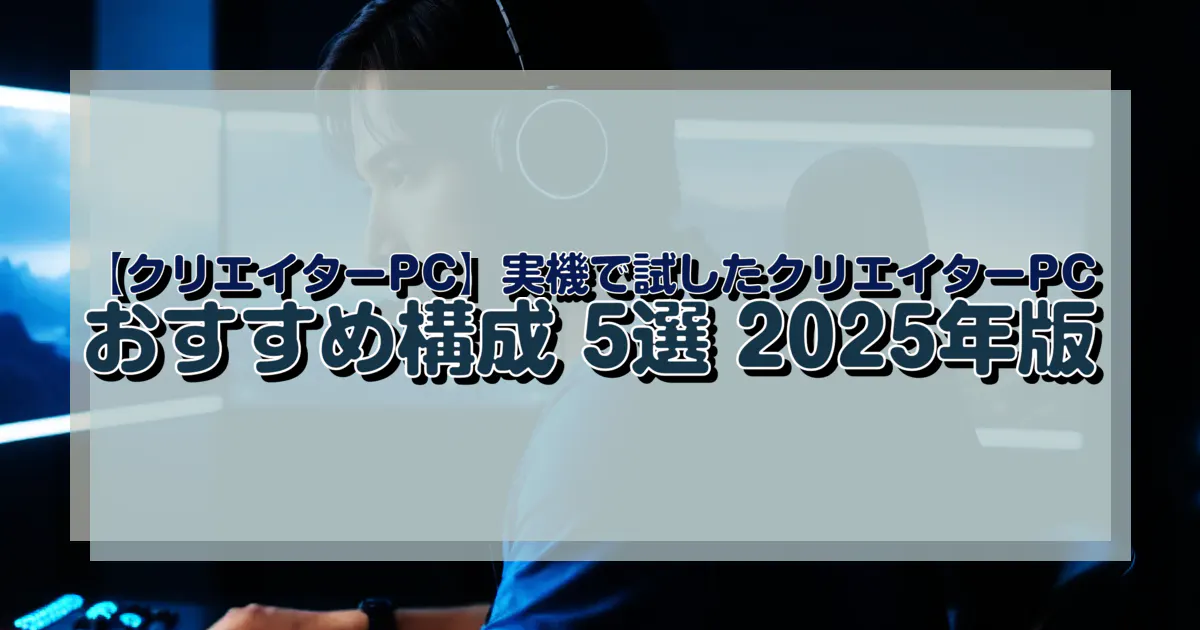最新CPUで組むクリエイター向けPCの実力と選び方のコツ
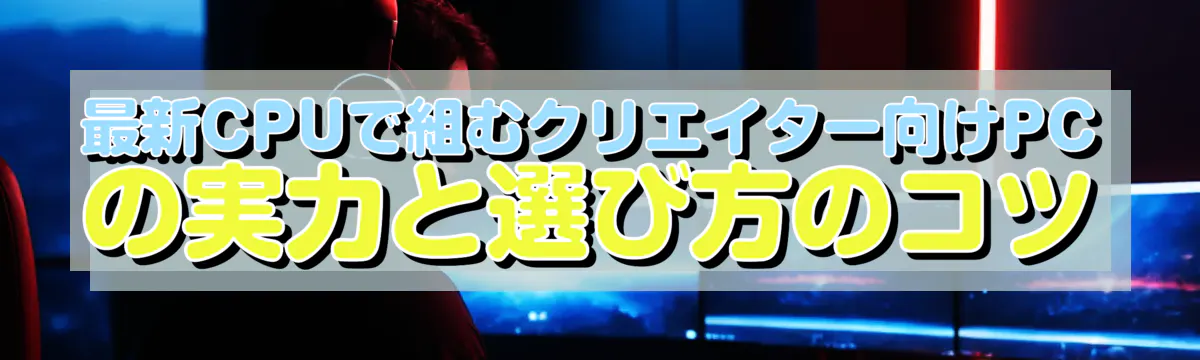
Core UltraとRyzen、実際に使うならどちらを選ぶか
私は最近、仕事と趣味の両面でCore UltraとRyzenを実際に触り比べてきました。
そのうえで率直にお伝えすると、もし本格的な動画編集や3Dレンダリングを業務レベルで日常的に行うのであれば、Ryzenを選んだほうがずっと効率が良いです。
理由はシンプルで、多コア構成による安定した並列処理のおかげで、重い作業でも処理が途切れないのです。
数時間単位で走らせるようなプロジェクトでも、安心して任せられる。
これは現場で働く人にとって非常に大きな価値だと思います。
ただ一方で、もし外出先での作業やモバイル性、そして新しいAI処理の快適さを求めるならばCore Ultraに分があります。
内蔵NPUの性能が想像以上に優れていて、GPUを外付けしなくても生成AIの処理がスムーズに動く。
それを体感したとき、私は「ああ、もうパソコンの使い方の常識が変わりつつあるんだな」としみじみ思いました。
正直なところ、これを一度経験してしまうと、従来の環境には戻りづらいとさえ感じる瞬間がありました。
特に印象に残っているのは、敢えて苦しい環境でテストをしたときです。
DaVinci Resolveで長尺動画を扱いながら、裏でBlenderのレンダリングも並行して走らせるという無茶をしてみました。
Ryzenのマシンはクロックが安定していて、プレビュー画面が驚くほどスムーズに動き続けたのです。
その瞬間、思わず声が漏れました。
「これはすごいな」と。
想像を上回る余裕に、少し鳥肌が立ちましたね。
一方、Core UltraではPhotoshopの生成塗りつぶしを試したのですが、外部GPUなしでこれほど滑らかに動くのかと心底驚かされました。
あのときの感覚はまるで、次の時代の入り口に立ったような感覚でした。
息を呑む、というのはこういうときに使う言葉なんだなと、妙に納得させられるシーンでした。
外出時の使い心地について触れると、Core Ultraの恩恵は本当に大きいです。
特にバッテリーの持ち具合。
体感で約1時間も長く使えるようになったのは、数字以上に意味のある違いでした。
モバイルワークというのは気楽さが全てですから。
一方で、デスクに腰を据えて本気の作業に取り組むときはRyzenが頼りになります。
その多コア性能とコストに対する性能比の高さは、今でも圧倒的に強い。
大規模な動画レンダリングや複数ソフトの並行作業など、PCに重い負荷を掛けるような実務では「やっぱりRyzenだな」と心から実感しました。
言葉を選ばず言えば、鉄板の選択肢です。
では実際にどう使い分けるのか。
私の答えは明快です。
日常的にAI関連タスクが多く、ノートPCでの作業が中心ならCore Ultra。
逆に大規模な映像制作やレンダリングを連続して処理しなければならない状況ならRyzen。
この切り分けが一番わかりやすく、実務的です。
私は自分の現場でもこの使い分けを徹底することで、ストレスなく両方を活かせるようになりました。
事務所に据え置きのRyzenと、外回りのCore Ultra。
自分にとって最も合理的な組み合わせです。
最近とみに感じるのは、PC市場全体でAI処理に舵を切っているという流れです。
アプリケーション側の進化も凄まじく、数年を待たずしてNPUの出番は飛躍的に増えていくでしょう。
その未来においてはCore Ultraの優位性はさらに高まると私は思っています。
ただし、だからといってRyzenが時代遅れになることはありません。
この二つの方向性が共存する市場があるからこそ、多様な働き方が可能になるのです。
つまり、Core UltraはAI処理やモバイル用途で輝く存在であり、Ryzenは長時間の安定処理という土台を支える存在。
そのどちらが優れているかと単純に比較するのではなく、自分の生活や仕事の優先順位にあわせて選び分けることが何より大切なのです。
同僚に相談されたときも、私はいつも同じことを伝えていますし、そのたびに「なるほど」と納得してもらえます。
選び方はじつにシンプルなのです。
私にとって、どちらか一方を手放す選択肢はありません。
結局のところ、両方を組み合わせることこそが一番の効率であり、精神的にも余裕を保つ鍵になるのだと実感しています。
自分の時間をどう守るのか、日々のストレスをどう減らしていくのか。
その答えの中にこそ意義があるのだと思います。
今の私にとって、それはRyzenとCore Ultraを使い分けることです。
少し贅沢かもしれません。
しかし、それが私にとってのリアルな答えです。
安心感。
頼もしさ。
動画編集を快適にこなせるCPU構成を探る
動画編集を楽に進めたいと本気で考えるなら、やはり最初に重視すべきはCPUの性能です。
特に高解像度の映像編集では顕著で、CPUが追いつかないと編集中のリズムがあっという間に壊れてしまうのです。
要するに、CPUを軽く見てしまうと結局一番苦しむのは編集している自分自身なんですよね。
動画編集でストレスを抱え込みたくないなら、多少高価でも多コアで高クロックのCPUを選ぶべきだと。
以前、8コアのCPUで4K映像の編集をしていたときのことを思い出します。
映像にエフェクトを重ね、トランジションを入れた途端、プレビューがカクついて何度も再生を巻き戻す羽目になったのです。
「もう勘弁してくれ」と本気で心の中で叫んでいました。
それが16コアのCPUに変えた瞬間、まるで別世界のように流れる。
エフェクトを加えてもカクつかないし、カラー調整を施しても安定している。
作業全体が途切れなく進んでいくことで、気持ちまで落ち着いて、前向きに取り組めるんですよ。
数字だけでは説明できない不思議な安心感。
この違いは人に話すより実際に体験してもらうのが一番早いと思います。
もちろんCPUが全てだとは言いません。
GPUやメモリ、ストレージとの相性も馬鹿にはできません。
ただ現実問題として、動画編集を続けていると一番先に限界を迎えるのはCPUであるケースが少なくないのです。
Premiere Proなどのソフトを使っていると顕著ですが、レンダリングの一部はGPUに任されるものの、音声や細かいカットの処理は基本的にCPUが担当します。
編集作業は集中の勝負みたいなものなのに、そこで作業を中断されることほどもったいないものはありません。
動画系のアプリに最適化されている点は本当に見事で、あれを触ったときの快適さは認めざるを得ません。
でも、Windows環境で幅広いアプリを併用する私のような立場だとIntelやAMDの多コアCPUのほうがまだ強みを感じる場面が多いのも事実です。
たとえば私が実際にRyzen 9を使ってDaVinci ResolveでH.265ファイルとRAW映像を扱ったとき、時間のかかる書き出しでも安心して放っておける安定感に「やっぱりこれだ」と深く頷いてしまいました。
長時間の作業中にフリーズしない。
その事実自体が大きな信頼につながるのです。
さらに、クロック速度の存在も忘れてはいけないと思います。
コア数が多いのはもちろん心強いですが、操作をしていて感じる瞬発力や小さなレスポンスの快適さはクロックの高さに影響されます。
窓の切り替えがサクサクと動く、タイムラインがピタッと滑らかに動く、それだけで「この環境で作業したい」と素直に思えるんです。
安定性と俊敏さ、その二つを兼ね備えたCPUに触れると腰を落ち着けて作業できる。
言葉にすると陳腐かもしれませんが、本当に戻れなくなる感覚があります。
私は過去に「安い構成で何とかなるだろう」と思って妥協したことが何度かあります。
しかしそのたびに作業時間が伸び、気持ちが折れ、最終的にもっと上位のCPUに買い替える結果になりました。
今振り返れば、最初から上を選んでおけば精神的にも経済的にもラクだったのにと後悔ばかりです。
だからこそ、私の経験を共有する意味でも声を大にして伝えたい。
動画編集に妥協は敵だと。
CPUに投資する。
それは自分の作業への投資であり、作業時間を削ること以上にストレスを軽減する投資です。
効率の良い環境は気持ちに余裕をもたらし、その余裕が新しいアイデアを生む土壌になる。
要するに、しっかりしたCPUを選ぶことで得られる価値は単なる時間短縮ではなく、クリエイティブな可能性そのものなんです。
私は自信を持ってそう言えます。
編集はリズムです。
選ぶ道具は妥協できない。
だから最終的に私が勧めたいのは、多コアであり、かつ高クロックを備えたCPU構成です。
それが安心して映像作品と向き合える環境をもたらし、集中力を最後まで切らさずに作業を進める後押しになります。
私はその信念を今も持ち続けています。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43074 | 2458 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42828 | 2262 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41859 | 2253 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41151 | 2351 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38618 | 2072 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38542 | 2043 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37307 | 2349 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37307 | 2349 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35677 | 2191 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35536 | 2228 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33786 | 2202 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32927 | 2231 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32559 | 2096 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32448 | 2187 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29276 | 2034 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28562 | 2150 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28562 | 2150 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25469 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25469 | 2169 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23103 | 2206 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23091 | 2086 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20871 | 1854 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19520 | 1932 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17744 | 1811 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16057 | 1773 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15299 | 1976 | 公式 | 価格 |
AI処理や3Dレンダリングに頼れるCPUの見分け方
AI処理や3Dの作業を本気で快適に進めたいのであれば、やはり軸になるのはCPUの選び方だと私は思っています。
GPUの派手な数値や噂にどうしても気を取られがちですが、結局のところCPUの性能が揃っていなければGPUが持つ力を最後まで引き出すことはできません。
だからこそ人に相談されれば「コア数とクロックのバランスが取れているCPUを優先したほうがいい」と、私は断言してきました。
派手さよりも土台。
ただ、単純にコア数だけを増やせば良いという話ではないのです。
以前、私は10コア搭載のCPUを導入し、期待を込めて3Dレンダリングを走らせました。
ところがクロックが低めの設計だったことが仇となり、プレビューでは重さが目立ち、カクつきに何度も苛立たされました。
その瞬間は正直「コア数が多ければ何でも解決する」と信じていた自分を情けなく思ったものです。
逆に最新世代の12コアでなおかつ高クロックのCPUを使ったとき、まるで景色が変わったかのように作業内容がスムーズに流れていったのを覚えています。
Blenderでのレンダリング時間は明らかに3割近く短縮され、並行してPremiereでの編集書き出しも止まることなく快走できたのです。
数字での違い以上に、その場で体感する安心感は大きな意味を持っていました。
生成系AIやStable Diffusionのような分野ではGPUが華であることは間違いありません。
しかしそこで忘れがちなのが、CPUが処理の前段を上手くさばかなければGPUの潜在力を眠らせたままにしてしまうという現実です。
タスク分配がもたつくと、作業者が感じるのは「待たされる時間」ばかりで、どれだけ高額なGPUを使っても全体の効率が下がってしまいます。
CPUとGPUは競合するものではなく、補い合って初めて両方が生きる。
ここを外すと大きな損失になると私は考えています。
実際、先月私は最新世代のハイエンドCPUを積んだワークステーションタイプのPCを手元で使う機会がありました。
動画編集から画像生成、さらには重量級の3D CADデータまで試しましたが、際立って印象に残ったのは処理能力そのものよりも冷却設計の安定感でした。
どんなに性能が高いと説明されていても、温度が上がった瞬間にクロックが落ち、力を半減させるようなCPUならば意味がありません。
高クロックを長時間維持し続けられること。
これが現場で仕事を回す上での本当の安心材料でした。
ただ残念なのは、大手メーカーの製品であっても意外と冷却の甘さが見えるモデルがあることです。
夏場に触っていて背中に嫌な汗が出てきた経験もありますし、「この設計では長丁場の編集は厳しい」とすぐ感じ取れる場面もありました。
結果として、本当に信用できるのは冷却面で投資を惜しまないモデルなのだと実感しました。
冷却の安心感。
では実際にCPU選びをどう進めればいいのか。
その答えは意外とシンプルです。
まず8コア以上の構成であること。
次に、クロックが高く長時間維持できる設計であること。
そして冷却システムが十分に考慮されていること。
この三点が揃っていれば、大半のクリエイティブワークでストレスは一気に減らせます。
理屈をこねるまでもなく、現場感覚で「楽だな」と思えるはずです。
ただし簡単に言っても、これらすべてを兼ね備えたCPUは決して多くはなく、自分の作業内容に最適な一台にたどり着くには調査や比較検討の時間が欠かせません。
動画編集を主とするか、AI処理を重点に置くか、その人の業務領域によって求める性能の優先度は自然と変わっていきます。
私のやり方としては、まず一番重く感じている日常作業を基準に置き、それに見合うCPU候補を絞るようにしています。
最初は遠回りに見えても、最終的には必要な性能が浮き彫りになる近道なのです。
CPUの動作クロックやスコアだけに目を奪われると、実際の作業環境で「なぜか体感が遅い」という違和感に直面することになります。
多くの人が見落としているこの冷却要素こそ、実務の安定度を大きく左右するのです。
私は過去に、真夏の室内で動画を書き出していたとき、CPUの温度が急に上昇して性能が一気に落ち、作業が失速してしまった経験を何度も味わいました。
その度に「冷却は削るべきところではない」と自分に言い聞かせてきました。
もし数万円を惜しんだことで仕事自体が止まるなら、それはあまりにも高い代償です。
そうやって痛みを伴いながら学んだ経験が、いまの私の判断基準を作っています。
要するに、AI処理や3DレンダリングのためのPCを選ぶ際に正解となるのは、高クロックのマルチコアCPUを選び、同時に冷却の設計が確かなモデルを選ぶことなのです。
たったこれだけのシンプルな基準ですが、これを守ることで大抵の作業は気持ちよく進行できます。
シンプルなだけに強い。
私はそう思っています。
安心して働ける環境があればこそ、成果が一番大きく返ってくる。
疲れてもなお粘れるのは、その環境が味方してくれるからなのです。
グラフィックボード別に考えるクリエイター向けPC例
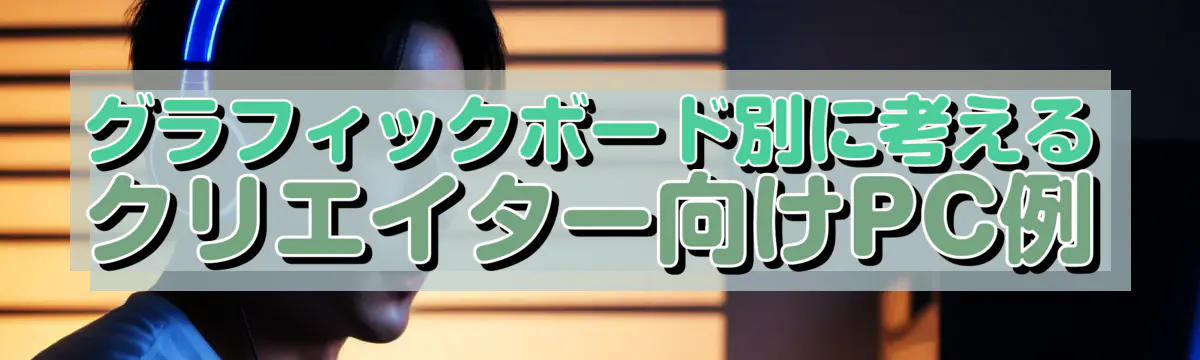
映像制作ではRTXとRadeonのどちらが扱いやすいか
映像制作の現場では、グラフィックカード選び一つで仕事のスピードや仕上がりの質が変わります。
私自身、何度も買い替えや組み合わせを試す中で痛感したのは、安定性を重視するならやはりRTXに軍配が上がるということです。
もちろん、Radeonも決して無視できない存在で、特にコストパフォーマンスや最新の配信形式を見据えた場合には選択肢に入れるべきだと感じています。
ただ仕事でミスや不具合を減らすという意味では、安心して頼れるのはRTXだと強く思います。
RTXを使用していると、Adobe Premiere ProやDaVinci Resolveといった主要ソフトの操作感がとても安定します。
プレビューで映像が止まらずスムーズに進むと、それだけで気持ちが救われます。
特に追い込みの納期前、再生がカクつかなかったりレンダリング待ちが少なかったりするだけで心の余裕が生まれ、「ああ、これなら間に合う」という実感が得られるのです。
焦る気持ちが抑えられる、この効果は仕事を長く続ける上で大きな意味を持ちます。
とはいえRadeonには興味深い瞬間もあります。
以前、8KのRED素材をRadeon RX 7900 XTで処理したところ、RTX 4080を使った場合よりわずかに早く書き出しが終わりました。
ただその優位性が常に発揮されるかというとそうではなく、環境やソフトの相性で結果は揺らぎます。
つまり絶対的な答えはなく、ケースごとの判断が必要だと感じました。
特に今の映像制作において避けて通れないのがAI機能です。
ノイズ除去や自動カラー補正などはもはや当たり前になっており、この点ではCUDAやTensorコアを搭載したRTXが圧倒的です。
AI処理をかけたときの処理速度差は実作業に直結し、数分の差が積もれば数時間の違いになります。
いや、本当に。
ところがRadeonも負けてはいません。
最近注目しているのはAV1エンコード機能です。
動画配信やSNS投稿用にAV1で書き出すと、ファイルサイズを抑えながら画質をしっかり守れるのです。
私も縦型のSNS用動画をRadeon環境で書き出したことがありますが、軽いのに画質が思った以上に綺麗で驚きました。
近年は高解像度でありながら容量を小さくした動画が求められていますから、この技術は無視できません。
AV1が主流になる未来を考えると、Radeonを意識しておくことは先行投資的な意味もあると強く感じます。
ただ実際の現場は理屈通りにはいきません。
クライアントに渡すものが予定通り完成してこそ信頼され、その積み重ねが仕事を次に繋げてくれます。
だからこそ私はRTXを軸に据えているのです。
しかし未来志向も必要です。
業界の流れは数年単位で大きく変化します。
今はPCでの仕上げが基本でも、次の10年ではSNS配信やモバイル閲覧を前提とした最適化が主流になる可能性が高い。
だから私はサブ環境にRadeonを取り入れ、案件ごとに相性や用途で使い分けています。
便利さだけでなく、予備の選択肢があることが自分に余裕を与えてくれる。
実際に両方を試していくと、それぞれの良さがあると同時に一方だけを選び切れない現実にも気づきます。
普段の編集業務を支えるのはRTXの快適さですが、新しい配信形式や軽量化技術に関してはRadeonが活躍する。
二段構えで構築したほうが、中長期的に見ると安定しながら進化に追随できるのです。
納期や安定性を優先するならRTXを迷わず選ぶ。
未来のフォーマットや配信市場を捉えるならRadeonを意識する。
そして二つを組み合わせる発想が、最も現実的で堅実な姿勢だということ。
数字では測れない安心と効率。
私はこれからもRTXを基盤に据えつつ、Radeonの進化を横目で確認していきます。
その過程で仕事に余裕を持ち、自分自身の判断力を磨き続けたいのです。
挑戦と安定。
その両立こそ、私が辿り着いた選択です。
3DCG制作で後悔しないGPUモデルの選び方
3DCG制作を本気でやっていこうとするなら、最終的にはGPUの選択がすべてを左右すると痛感しています。
数字上の性能差なんてカタログを見ているだけでは大した違いに感じないものですが、実際に使い込んでみた瞬間、その差がどれほど大きな意味を持つのか、嫌でも体で理解させられる。
レンダリングや生成AIの処理では、わずかな性能差が数時間単位の生産性の差として表れることがあるのです。
あれほど残酷に時間を奪われる場面はありません。
私はRTX 4090を選んで後悔したことは一度もありません。
24GBのVRAMが生む安心、そして圧倒的な処理性能。
どれも「ただの数字」で片付けられるものではなく、むしろ作業中の心の余裕にダイレクトにつながるのが大きいのです。
例えば大規模なシーンを組み上げても、GPUに余裕があると落ち着いて操作を続けられる。
作業が止まるかどうかという小さな違いが、気持ちの面ではとんでもなく大きな意味を持つんですよね。
安心感。
かつて私はRTX4060 Tiをメインに仕事を回していました。
モデリングや軽めのアニメーションなら快適で、あの頃は「これで十分いける」と本気で思っていました。
ただUnreal Engineで大きめの背景を作り込んだ際、ロード待ちで何度も作業が中断し、プレビューはガクガク、気づけば夜中になっている。
正直言って、あの焦りと苛立ちは今でも苦い記憶として残っています。
「こんなことで仕事に支障をきたすのか」と呆然としましたね。
そこで思い切ってRTX 4080へ乗り換えたのですが、その瞬間から作業の流れは劇的に変わったんです。
それまでの待ち時間はほぼ消え、同じタスクをずっと短い時間で片付けられるようになった。
正直、「もっと早く決断しておけば」と悔しさが込み上げてきました。
これが現実なんです。
だからこそ声を大にして言いたいんです。
GPU選びは単なるコストの話ではない、と。
効率的に、そして心を削られずに作業を続けるための根っこを支えているのがGPUで、そこに惜しむ気持ちを持ち込むべきではないと考えています。
毎日の疲労やストレスまで影響を受けるんです。
最終的にパフォーマンスの頂点である4090に投資する意味はここにあります。
例えば中規模案件を中心に扱う方なら、RTX 4070 Ti Superという選択は十分に理にかなう。
12GBのVRAMも工夫次第で使いこなせますし、価格や消費電力を含めた全体バランスは本当に優秀です。
ただ一方で、重い生成AIのプロジェクトを並列で動かしたい時などは、正直に言って物足りなさが顔を出す。
最近、生成AIベースの動画生成サービスをテスト的に使う機会がありました。
軽く試すつもりだったのに、いきなり20GBを超えるVRAMを要求され、思わず「え?」と声が出ました。
自分の中では16GBでも余裕があると思っていたので、あの瞬間は冷や汗もの。
24GBを載せた4090を選んでおいて良かったと、しみじみ実感しました。
やはり備えあれば憂いなしなんです。
GPUの選び方は結局、自分がどこまで本気でやっていくかに帰着する。
学びや趣味レベルなら3060 Tiで十分に入り口に立てます。
しかし、プロとして作品を外に出し、クライアントワークをこなしていくのであれば、4090の導入は冷静かつ現実的な選択です。
だって、これは単に機材を買うのではなく、自分の時間を買うことだから。
冷静にいえば、余計な待ち時間をお金で削減する行為なんです。
夜中にレンダリングが終わるのを延々と待ち続けるむなしさ。
さらに「修正お願いします」と連絡が入り、もう一度最初からやり直すためにまた数時間を費やす。
この繰り返しに耐えるのか、それともGPUの力を借りて早く終わらせ心に余裕を持つのか、その違いは長い目で見れば大きな道筋を分けることになるんです。
だから私の答えは明確です。
覚悟を決めてプロとして突き進むなら4090しかない。
中規模の仕事で安定感とのバランスを取りたいなら4070 Ti Super。
学習や小規模な挑戦を中心にするなら3060 Tiでも十分。
ただ後悔を避けたいのであれば、やはり4090。
それが私自身の実感であり、積み重ねた経験から出した正直な結論です。
信頼できる相棒。
仕事で共に戦うパートナー。
GPUという一枚の基盤に、ここまで感情を注ぐようになるとは昔の私なら笑っていたかもしれません。
しかし今なら言えます。
GPUを軽く見てはいけない。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48704 | 101609 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32159 | 77824 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30160 | 66547 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30083 | 73191 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27170 | 68709 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26513 | 60047 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21956 | 56619 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19925 | 50322 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16565 | 39246 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15998 | 38078 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15861 | 37856 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14643 | 34808 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13747 | 30761 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13206 | 32257 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10825 | 31641 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10654 | 28494 | 115W | 公式 | 価格 |
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54AS

| 【ZEFT Z54AS スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59YA

| 【ZEFT R59YA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56E

| 【ZEFT Z56E スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G08H

| 【EFFA G08H スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60BS

| 【ZEFT R60BS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
4K映像編集を安定させるためのグラボ選択のポイント
4K映像編集を真剣に行おうと考えたとき、私が一番大切だと痛感するのはグラフィックボードの性能です。
理由は単純で、これを甘く見てしまうとどんなに高価なPCを揃えても、結局は途中で作業が止まり、やる気までごっそり持っていかれるからなんです。
性能は単なるスペック表の数字にとどまらず、実際の編集の快適さやプレビューの滑らかさ、さらには書き出しにかかる時間に如実に差となって現れる。
この点を軽んじると、本当に後悔しますよ。
私は数年前にRTX4060を使って4K編集を試した経験があります。
あのときは素材にカラー補正をいくつも重ねた瞬間、プレビュー画面が途端にカクカクと動き始め、「え、もう限界?」と声が漏れてしまったのを今でも覚えています。
あの瞬間、作業を続ける気力が一気に削がれた。
作業の流れが止まらないというのは、単に速いとか快適ということを超えて、仕事そのものへのモチベーションを守ってくれるものなんです。
もちろん性能だけでなく、安定性も大事です。
ここを軽視すると必ず痛い目を見ます。
どんなに高性能なゲーミング向けカードでも、編集用途ではドライバによって大きな差が出る。
仕事で実際に役立ったのはNVIDIAのStudio Driverでした。
Premiere ProやDaVinci Resolveに合わせて綿密に調整されているため、まるで専門のサポートを横につけてもらったような感覚があり、その安心感は一度体験すると手放せない。
一般向けドライバとの差は明白で、私はそれ以来「安定性にお金を払う」という価値を強く感じるようになったのです。
4Kプロジェクトは素材の容量が膨らみがちで、これも悩みのひとつです。
短編であればそこまで問題にならなくても、長編ドキュメンタリーや複数台のカメラで撮影した案件では、驚くほどの速さでVRAM不足に陥ります。
するとプレビューが止まり、いやでも作業が中断される。
納期に追われているときにこれが続くと、本当に精神的にきついんです。
RTX4080 Superや4090のように16GB以上のVRAMを積んだモデルに変えた瞬間、そのストレスがきれいに消えてしまったのは衝撃でした。
AIによるノイズ除去やカラー補正がリアルタイムで回るようになり、仕事が快適に流れる。
その解放感と安心感は、数字以上のものです。
問題はやはり価格ですね。
こればかりは現実的な壁です。
正直、ミドルクラスとハイエンドの差額を見たとき、私自身も最初は躊躇しました。
買う前は「さすがに高すぎるだろう」と思わずため息をついたほどです。
けれども作業時間を何十時間も短縮できることや、トラブルによるストレスをぐっと減らせることまで天秤にかければ、その出費が高すぎるとは言えない。
むしろ、結果として自分の時間や心の余裕を買っているのだと、私は仕事の現場で痛感しました。
はっきり言います。
4K編集に挑むのなら、無理にミドルクラスを選ぶ理由はない。
少なくとも16GB以上のVRAMを搭載し、Studio Driverに最適化された上位モデルに投資するべきです。
私は声を大にして言いたい。
「もし迷っているなら、投資を選べ」と。
たとえ初期費用が高くても、後々の効率や納期の安定感を得られるなら、結局は得する道しか残っていません。
実務の現場では、作業効率がそのまま信頼に直結します。
私自身、過去にグラボを妥協したせいで納品に時間がかかり、苦い経験をしたことがあるからこそ、その重要性を強く感じています。
RTX4080を導入してからの開放感は、そうした過去の苦労を晴らしてくれるものでした。
作業が止まらない安心感。
そして、無駄に焦らなくて済む気持ち。
この二つを得るために出費を重ねる価値は、間違いなくある。
見た目の金額だけを追いかけると損に感じてしまうかもしれませんが、最終的に得られる信頼や時間、さらには自分の精神的な余裕を考えれば、先行投資にほかなりません。
どこに優先順位を置くかは人それぞれです。
ただ、本気で4K編集に取り組むなら、性能を惜しまない選択肢をおすすめします。
その分岐点は、最後にはグラフィックボードの一枚で決まるものだと、私は自分の経験から断言できます。
クリエイター用PCに合うメモリとストレージの考え方
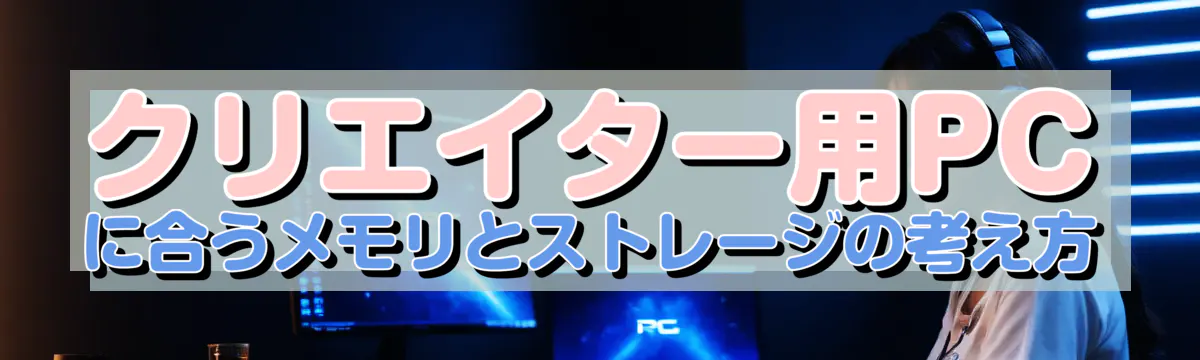
32GBか64GBか、作業内容で変わる最適容量
パソコンのメモリ選びというのは、単なるスペック表の数字で片づけられる話ではなく、実際の体験を通して「これはどうしても必要だ」と心から納得できるかどうかに尽きるのだと思います。
私の経験から言えば、映像編集を本格的に行うなら64GBを選んでおくことが間違いなく安心だと断言できます。
一方で、写真加工やイラスト制作、あるいは音楽制作の用途であれば32GBで十分に快適に作業ができます。
つまり、メモリ容量の最適解は人によって違い、自分がどこに時間を注ぐのかで決まるのです。
私は数年前、Premiere Proを使って4K映像のマルチカメラ編集に初挑戦したことがありました。
意気揚々と作業に取りかかったのですが、32GB環境ではほんの少しタイムラインを動かしただけでカクつきが発生し、まともに再生確認もできませんでした。
そのときは本当に焦り、無駄に冷や汗をかいてしまい、作業が進まない苛立ちだけが積み重なるばかりでした。
ところが、意を決して64GBに増設した瞬間、再生がまるで別物のように滑らかになり、映像の流れをストレスなく追えるようになったのです。
その差を目の当たりにしたとき、数字の裏にある「現場でのリアルな影響」を痛感しました。
机上の理屈じゃない。
実際の作業の快適さです。
とはいえ、何もかも64GBが正解というわけではありません。
私はLightroomとPhotoshopを同時に立ち上げてRAW現像やレタッチ作業をすることがよくありますが、その程度なら32GBでも問題なく回ります。
むしろ余裕すらある印象です。
音楽を流しながらブラウザで調べものをしつつ、写真編集をしてもカクつくことはありません。
64GBに増設してからメモリ使用率をモニターした際には、「あ、だいぶ余らせているな」と思わず苦笑してしまったほどです。
無駄感。
他の人なら「宝の持ち腐れ」と突っ込みそうな状態でした。
ただし、After Effectsを使った映像編集となると話は別でした。
複数のコンポジションを重ね合わせて映像を細かく構成していく作業では、メモリの余裕がものを言います。
プレビュー再生が速くなり、レンダリングの待ち時間が明らかに減ったのです。
作業が中断されないことで集中力が保たれ、納期ギリギリのときでも落ち着いて仕事を進められる。
この安心感はとても大きい。
映像が本業の人間にとっては、もはや欠かせない存在だと実感しました。
さらに、ゲーム配信と動画編集を同時に行うシーンでも差が出ました。
OBSと映像編集ソフトを同時に実行すると32GBではどうしても動作が重くなり、余計なアプリを一つひとつ閉じなければならなくなります。
64GB環境にしたらその必要がなくなり、録画も編集も同時に快適に動作しました。
作業を中断せずに続けられる環境というのは生産性を大きく底上げしてくれるものです。
作業の流れが止まらない。
それだけでこんなに快適なのかと驚きました。
正直言うと、私自身ここまで差があるとは予想していませんでした。
32GBでも十分だろうと考えていた自分を、体験があっさり裏切ってきたのです。
そのときの衝撃は、初めて最新のAIによる動画生成サービスを試したときの感覚に近いものでした。
PCメモリの差でさえ、似たような感覚を味わうことになるとは、正直思いもしませんでした。
一方で、冷静に考えれば選び方はシンプルです。
逆に、主に写真加工やイラスト制作を行っているだけならば32GBでも十分で、コストを合理的に抑えることができます。
私は単に「余裕を見ておくために大きい方を買うべきだ」という考えには懐疑的です。
むしろきちんと作業内容に即して選ぶべきです。
無駄を省いて、本当に必要な部分に必要な投資をする。
迷っている人に伝えたいのは、まずは「自分がどの作業にもっとも時間を費やしているか」を明確にすることです。
もし日々の大半を映像制作に割いているのであれば、迷うことなく64GBにした方が後悔はありません。
一方でイラストや写真加工を中心にしているのであれば、32GBで十分です。
余裕があるからといって64GBを入れても、持て余すだけで効果を感じにくいことも多い。
この違いに早めに気づければ、無駄な投資は避けられます。
私は改めて振り返って思うのですが、メモリというのは不足すれば作業を止めてしまう要因になり、多すぎると眠らせてしまう厄介な存在でもあるのです。
幸い映像や写真の仕事をしてきた中で何度も試してきましたが、その結論は一貫しています。
容量さえ自分にとって適正なら、作業効率で不満を感じることはほぼありません。
安心感。
だからこそ私は、自分の実体験をもとに断言します。
映像を本業にしている方は64GB。
それが現実的で、もっとも無駄のない選び方です。
最終的に辿り着いた答えは、予想以上にシンプルでした。
私はそう強く思います。
PCIe Gen5 SSDは編集作業に本当に必要なのか検証
PCIe Gen5 SSDについて冷静に考えると、少なくとも映像編集を日常業務としている私にとっては、現段階で積極的に導入すべき理由はほとんど見当たりません。
一般的な4K映像編集や静止画のレタッチであれば、PCIe Gen4 SSDでも十分すぎるほど快適に動作しますし、実際に現場で使っていてあれこれアップグレードしなければと焦らされる場面は皆無だったのです。
誤解を恐れずに言えば「スペックの数字はすごいが、現実の仕事では差を感じにくい」というのが素直な実感です。
私は以前、Samsung製のGen4 SSDを2TBモデルでRAID 0に組み、Premiere Proで複数の映像レイヤーを同時にプレビューしたり、書き出し検証をしたりしたことがあります。
そのときの体験は驚くほど快適で、シーク操作や書き込み動作で立ち止まるようなストレスは一度もありませんでした。
思わず「これで十分だ」と口に出してしまったほどです。
安心感。
しかしGen5を導入してみると、少なくとも私の日常業務においては「極端に大容量で数テラバイト規模のファイルを、ほぼ休みなく移動し続ける状況」においてしか性能の差を実感できませんでした。
それ以外の場面では、正直「ここまでお金をかける必要があるのか」と首をかしげたくなることばかりです。
数字で眺めるベンチマークは確かに圧倒的に速いのに、実仕事ではその実感につながらない。
ギャップに苛立つ瞬間、正直にありました。
これは例えるなら、最新スマートフォンのカメラが夜景をやたら鮮やかに見栄え良く加工して見せるけれど、実際に自分の目で見た風景とはちょっと違うというあの違和感に近い。
派手ではあるが、肝心の実用では肩透かしを食らう。
そんな体験です。
ただ、だからと言ってGen5 SSDを完全に否定してしまう気はありません。
CPUやGPUが進化し、AI処理が常時ストレージへアクセスするような時代がやってくるのは、それほど遠くない未来でしょう。
そのときにはGen4の帯域では足りず、Gen5以上が標準になっていくのは容易に想像できます。
未来を見据え、余裕のあるうちに慣れておきたいと考える人が導入する意義は確かにありますし、試験的に現場へ組み込む判断も理解できます。
要は「今の業務に見合うかどうか」が本質だと思うのです。
一方で現状のGen5 SSDには、私個人としてどうしても気に入らない点もあります。
それが冷却構造です。
大型ヒートシンクを強引に載せただけのような設計が多く、メンテナンス性や取り回しやすさという観点が軽視されているように見えてしまう。
パーツ交換のたびに余計な手間がかかるのは正直げんなりしますし、日々数多くの機材を触る私のような立場からすると、作業効率を落とす要素でしかありません。
メーカーには、「数字の性能だけでなく人間が扱う便利さ」をもう少し真剣に考えてほしいと強く願います。
扱いやすさ。
ではどうするのが現実的なのか。
私が導き出した答えは明快です。
映像編集を基盤にPCを構築するなら、メインはPCIe Gen4 SSDの2?4TBを据える。
それに加え、必要であればセカンダリとして大容量のSATA SSDやNASを組み合わせる。
これがコストと実用性の両面から見てもバランスの取れた形です。
そして、Gen5 SSDを本格的に検討すべきなのは、ごく一部の特殊なプロジェクトを扱う人、もしくは最新技術に触れ、自分自身で結果を試したいという余裕がある人に限られる。
そこが冷静に見極めるべきラインなのだと思います。
かっこよく言えば最先端の性能であり未来を先取りする装備ですが、もし日々の仕事に即効性がないのなら、それはただの自己満足で終わってしまう可能性が高い。
実用か幻想か、その見極めを誤ると後悔しか残らないと、私は身を持って痛感しました。
迷ったときは、いつもシンプルに「それを使う自分が気持ちよく仕事に打ち込めるか」で考えるのが一番です。
派手な広告や数値の羅列に振り回されるのではなく、机の上で実際に汗をかいている風景を想像しながら判断する。
そして今の私にとっての答えは、いたって現実的なものです。
PCIe Gen5 SSDは魅力的ではあるが、今はまだ必要ない。
未来を意識しつつ、現場の今を大事にする。
それが私の選択です。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
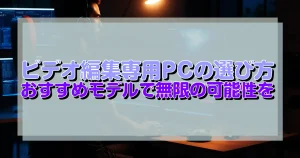



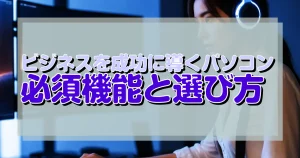
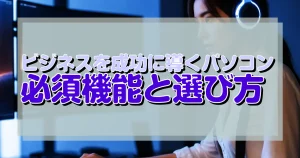
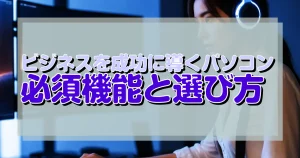



SSDメーカー選びと容量の決め方の実体験
私はこれまで数多くのPC環境で作業をしてきて、そのたびにストレージ選びで頭を悩ませてきました。
特に動画編集や3Dモデリングを伴う仕事では、SSDの性能がはっきりと仕事の効率に直結するため、どれを選ぶかで一日の進み具合がまるで違ってくるのです。
なぜなら速度と安定性が程よいバランスで共存しており、安心して長時間のプロジェクトに向き合えるからです。
実際、編集中にSSDが息切れを起こすと、気持ちごとブレーキがかかる。
そんな経験を繰り返してきました。
だからこそ「止まらないこと」が何より重要だと痛感したのです。
Gen.5も試してみました。
確かにベンチマークや最初の数秒は目が覚めるような速さで、それを初めて体験したときは思わず「これぞ次世代か」と声が出ました。
しかし問題はそこからです。
実際、レンダリングが途中で遅れ始めて焦りながら冷や汗をかく場面がありました。
その瞬間「ああ、これは運用するには無理があるな」と悟りました。
派手さに心を動かされても、現場では結局ストレス源になってしまうのです。
それに比べればGen.4は落ち着きがあり、扱いやすい。
速度は必要十分で、安定感が当たり前のように続いてくれる。
それがどれほど精神的に支えになるか、実際に仕事をしてきた方なら分かるはずです。
高価なGen.5をわざわざ取り入れるより、最初からGen.4を軸にしたほうがコストも含めて合理的。
冷静に考えれば、毎日の作業を途切れさせない環境づくりこそが結果的に最も効率を高める投資なのだと思います。
一方で、コストを重視するならCrucialやキオクシアの1TBから2TBモデルも十分に選択肢になります。
私は過去に作業用と保管用を一緒のドライブで回していましたが、これを明確に切り分けたことでプレビュー落ちが激減しました。
編集がスムーズに進むようになると、それだけでモチベーションも維持されます。
大規模な映像案件を扱うこともあるので、4TB以上のSSDを導入する場面もありました。
このほうがデータの整理やアーカイブが明確になり、あとから探す際に混乱せずに済みます。
私はかつてひとつのドライブに全データを放り込み、結局どこに何があるか分からず苦労した経験があるので、同じ失敗はしたくないと思うようになりました。
メーカーに関しても使い分けの知恵があります。
WDは信頼性が強くて、正直トラブルが少ない印象があります。
Crucialはバランス型で、価格と速度の折り合いがちょうどよく、コスト意識の強いプロジェクトでは心強い。
キオクシアは冷却が比較的楽で、大きなファイルを何度も転送しても安定性を崩さない。
動画中心ならWD、写真編集ならCrucial、大量コピーならキオクシア。
机上のスペックだけでは語れない領域なんですよ。
そしてBTOショップ選びも欠かせません。
私はHPのワークステーションを長く使ったことで、安心してSSDを積める基盤の大切さを実感しました。
マウスコンピューターは映像編集者に寄り添った構成が豊富で、カスタムに柔軟に応えてくれる点が魅力です。
さらにパソコンショップSEVENの存在感も無視できません。
ゲーミングのイメージが強いかもしれませんが、実際はクリエイターにも頼られている。
Gen.5や大型ヒートシンクなど最新仕様にも対応し、サポート体制が非常に手厚い。
これは本当に心強いですし、「ああ、信頼できるな」と感じさせられます。
サポートは軽視してはいけない。
結局のところ、私が整理した答えはこうです。
まず仕事用SSDの軸はWD Gen.4の2TBに据える。
そしてCrucialやキオクシアを自分の用途や予算に合わせて組み込む。
導入先はHP、マウス、パソコンショップSEVENを状況に応じて選ぶ。
こうした判断を積み重ねることで後悔は確実に減ります。
正直これが一番しっくり来ます。
私は40代になって、ようやく「最新が正義」という感覚から自由になれました。
技術に夢中になる気持ちもまだ残ってはいますが、それ以上に大事なのは安定して自分の仕事を支えてくれる環境です。
SSD選びにおいても同じで、自分の作業リズムを邪魔せず支えてくれるものこそ価値がある。
無理なく落ち着いて付き合える選択。
静かで安定した作業を支えるPC冷却構成
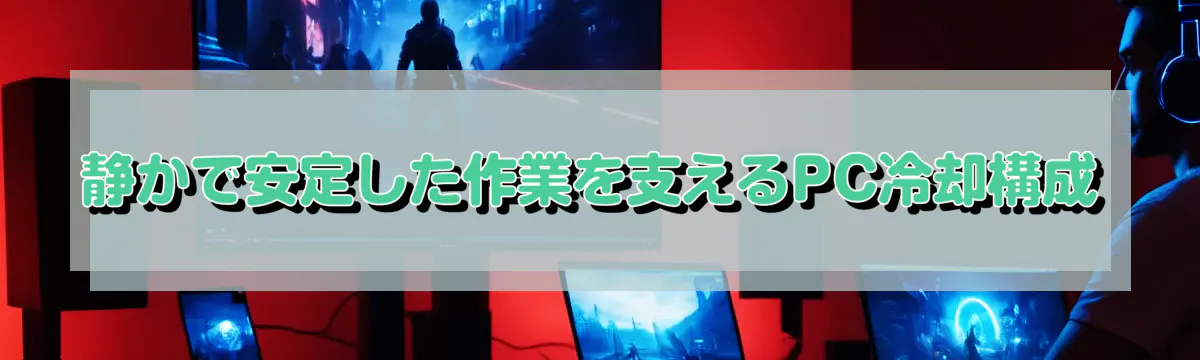
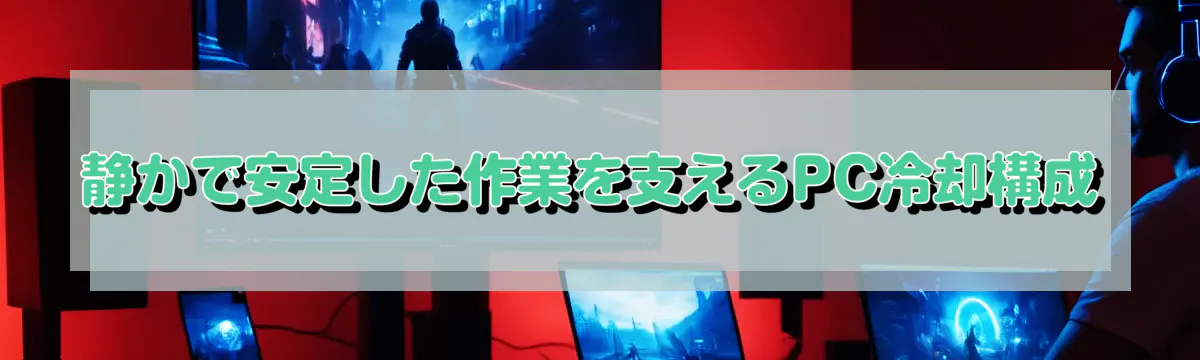
空冷と水冷、制作時間が長い人に向くのはどっちか
私は長時間にわたって高負荷な作業を続ける環境では、水冷システムのほうが圧倒的に安心できると実感しています。
空冷でも日常的な用途なら問題はなく、数年単位で快適に利用できることも体験してきましたが、真夏の部屋で高温が続くと途端に限界が訪れる。
CPUが頭を抑え込まれるようにスピードを落とし、作業画面がギクシャクと止まるあの瞬間のがっかり感は今でも強く覚えています。
自分の集中力まで一気に冷めるのです。
だからこそ水冷を導入したときの衝撃は大きかったです。
ラジエーターを大型のものに交換し、数時間にわたり複数のアプリケーションを同時起動しても温度がほとんど動かない。
その余裕がもたらす安心感は、単なる冷却性能の数字以上に大きなものがありました。
外部配信をしながら編集とデザインを並行するという、以前なら怖くて挑戦できなかった状況でも動作が滑らかに保たれていた。
あのときは「もっと早く乗り換えておくべきだったな」と心から呟きました。
一方で、空冷の魅力を簡単に否定してしまうのも違うと思っています。
実際に初めて自作したPCは空冷でしたし、トラブルもなく数年使い続けられた。
ファンの取り付けもシンプルでメンテナンスらしい手間も不要、コストも抑えられる。
だから最初の一歩として空冷を選ぶことに十分な理由はあると、今でも考えています。
ただ私自身の立場――制作現場で時間を忘れて集中し続けることが求められる役回りでは、やはり水冷の安定性を犠牲にはできません。
例えばAI画像生成案件でGPUを丸一日回しっぱなしにしたとき、水冷で構成していたからこそ最後までクロックダウンが起きなかった。
仕事は信頼がすべてです。
その緊張感を抱えずに済むのは大きな救いでした。
もちろん水冷には弱点もある。
もし内部で冷却液が漏れれば被害は甚大。
考えるだけで背筋が冷えます。
だから導入する際にはリスクを理解し、少しでも信頼できる部品を選びたいと自然に身構えるのです。
それでも私はあえて水冷を選びます。
制作を止めないために。
若い頃はとにかく効率とスピードを優先していました。
多少動作が重くなっても「まあ何とかなる」と目をつぶっていた。
けれど40代になり、案件を同時並行で回し、家族や他の責任も背負う立場になった今、途中で止まる不安を抱えたまま仕事を続けるストレスが耐え難くなってきました。
精神的にも落ち着いて取り組める環境こそ、一番の成果を出すための基盤だと感じています。
安心して挑める仕事場。
これに勝るものはありません。
制作を邪魔されない。
この一点が最大の価値です。
趣味での利用なら妥協もできるかもしれない。
けれどもビジネスの現場では時間を無駄にする余裕はないのです。
そのためには安定した環境への投資を惜しまないことが欠かせないと、今は胸を張って言えます。
私はこう考えています。
空冷か水冷か、結局のところ求めるものによって最適解は変わる。
音の静かさや経済性を大事にする人には空冷が合っているでしょうし、長時間安定して作業を続けたいのであれば水冷が圧倒的に有利になる。
ただ「制作を止めない」という一点を優先したい人には迷わず水冷を推したい。
なぜなら仕事で失う一瞬の信頼、それを取り戻すのにかかる労力は想像以上に大きいからです。
安心感。
これがすべてを左右します。
静かに、そして確実に動き続けるマシンはただの仕事道具ではなく、自分の背中を支えてくれる相棒のような存在になります。
私にとって水冷を選ぶ理由は単純です。
制作を最後まで止めないため。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CI


| 【ZEFT R60CI スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54AO


| 【ZEFT Z54AO スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R47AV


熱戦必勝!高級アッパーハイレベルのゲーミングPC、揺るぎないパフォーマンスの新モデル
32GB DDR5メモリと1TB NVMe SSDでスピードと容量、最適なバランスのスペックを誇る
NZXT H9 ELITE WHITEケースで、スタイリッシュに、クールに姿を変えるマシン
Ryzen9 7900X搭載、処理能力の極みを実感せよ!新世代CPUの力を体験
| 【ZEFT R47AV スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7900XTX (VRAM:24GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R55AC


プレミアムな体験をコミットするゲーミングPC、速度とパワーを追求したアドバンストモデル
最新のゲームに最適なバランス、RTX 4060と高速DDR5で現代のプレイをスムーズに
RGBが煌めくFractalの筐体で、部屋も次世代のコンピューティングに照らされる
Ryzen 5 7600搭載、最新技術で応答性高く作業も遊びもレベルアップ
| 【ZEFT R55AC スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 7600 6コア/12スレッド 5.10GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
長時間稼働でも安心できたCPUクーラー3選
冷却にこだわるというのは、ただパソコンの部品を守るためではなく、自分の仕事の質や成果物の信頼性を守るためなのだと私は実感しています。
特に映像編集や3DレンダリングのようにCPUを長時間酷使する作業では、ほんの少しの冷却不足が処理の遅延につながり、気づかないうちに作業全体の効率を落としてしまうのです。
だからこそ冷却性能と静音性、この両方を満たしたCPUクーラーが欠かせない。
正直、これを軽視して痛い思いをしたことも一度や二度ではありません。
今回あらためて私が信頼できると感じたCPUクーラーを3つ紹介します。
最初に挙げたいのはNoctua NH-U12Aです。
実のところ私はずっと空冷派で、水冷を導入したこともありましたが面倒さに嫌気が差して戻ってきた経験があります。
このモデルを使った時、「空冷ってまだまだやれるじゃないか」と率直にうれしくなりました。
夜を徹してレンダリングしてもファンの音が小さく、隣の部屋で寝ている子どもを起こす心配さえないほどの静かさ。
目の前の作業だけに集中できる環境というのは思った以上にありがたいんです。
音に神経を削られずに済む。
それがここまで違うのか、と改めて感じさせられましたよ。
次にCorsair iCUE H150i Elite LCD。
これは冷却性能と遊び心をうまく両立させているモデルだと強く感じました。
たとえば生成AIの処理を数時間回してもポンプ音が安定していて、不快な振動もほとんどないんです。
その上で液晶にCPUの温度や使用状況がリアルタイムに表示される仕組みは単なる飾りではなく、本当に頼もしいサポートになります。
実際に作業中「温度大丈夫かな」と気になったとき、画面で数値を確認してホッとすることができました。
目で確認できる安心感。
小さな配慮が最終的には大きな集中力の差につながるという実感を持ちました。
そして最も心を掴まれたのがbe quiet! Dark Rock Pro 5です。
空冷にもかかわらず水冷と肩を並べる性能を備えており、しかも取り付けが格段に楽になった点には驚かされました。
慌ただしい仕事の合間に余計な苦労をせずサッと組み込めるのは本当にありがたい。
数日間にわたり高負荷の作業をかけても真夏の室温でさえ熱に負けない安心感。
これはまさに頼れる相棒だと思いました。
安心。
これは積み重ねです。
1回や2回の動作で判断できるものではなく、何度も高負荷の作業を繰り返す中で「このクーラーは信じられる」と自然に思えることが大切になります。
ビジネスで考えれば冷却の選択を誤るのは、大事な商談にろくに準備をせず臨むようなもの。
そんな無謀な選択は誰もしたくないですよね。
ただ冷えればそれでいいというものでもありません。
私自身、強力な冷却性能をうたう製品を選んでファンの騒音に苦しめられた経験があります。
結局そのせいで作業に集中できず本末転倒でした。
また取り付けが難しい製品だと、メンテナンスやパーツ交換で余計な負担を背負うはめになる。
その意味でも冷却力と静音性、扱いやすさ。
今回紹介した3モデルは、その点どれも納得できるものでした。
Noctuaは静音と冷却力の実直な両立。
Corsairは性能と分かりやすい視覚的サポート。
be quiet! はパワフルな冷却と取り付けやすさ。
どれを選んでも外れはないと自信を持って言えます。
もちろんケースサイズや好みによる調整は必要になるでしょうが、長時間の仕事を託せるという安心感は共通しています。
だから小さなパーツ選びを軽んじることはできなくなったんです。
CPUクーラー一つとっても妥協したくない。
それは最終的に自分自身を守ることにつながるからです。
冷却に悩んでいるなら、この3つから選べば間違いない。
静かに冷やしてくれる。
その安心感は仕事の効率を底上げしてくれると私は信じています。
もう迷う必要はないんです。
PCケースで意外と変わる冷却性能の違い
これは私自身が身をもって体験してきたことなので、強調して伝えたいのです。
世間一般ではCPUやGPUといった性能部分にばかり注目が集まりがちですが、実際にはケースの設計次第でその性能が活きるかどうかが決まります。
見た目は単なる箱のように見えても、実は中身を守り、安定的に動作させる土台こそがケースなのです。
昔の私はそこまで深く考えていませんでしたが、あるトラブルをきっかけに意識が大きく変わりました。
するとCPUの温度差が実に8度以上もありました。
冷却が不足していると無駄にファンが全開で回り続け、結果的に騒音も電力消費も増えていく。
作業環境の快適さが日に日に削られていく感覚でした。
いや、これは本当に辛い。
そして実際に使ってみて気づいたのが、体験としての安心感です。
冷却性能がしっかりしたケースで作業するのとそうでない場合とでは、心の余裕がまるで違います。
機械の調子に左右されず、作業に集中し続けられる。
落ち着いて取り組めるというのは何よりも貴重です。
また、ケースの設計は単に筐体という枠にとどまらず、空気の流れそのものをデザインする役割があります。
前面から十分に吸気できるモデルはGPUの発熱をうまく抑えてくれましたが、ガラスパネルを多用したモデルは見た目の美しさこそあれ、空気の流れがどうしても滞りがちでした。
ちょうど換気の悪い会議室に大人数が集まったような不快感です。
こればかりは体験して初めて実感できることで、スペック表だけでは絶対に分からない現実です。
つい先日も、厚みのある最新GPUを組み込んだ際にフロントからの冷却風が全然届かず、温度が急上昇するのを目の前で見たことがありました。
その瞬間は冷や汗もので、思わず「これはいかん」と声が出ました。
実体験からの学びは、机上の知識よりずっと深く腹に落ちます。
ここまでの経験を踏まえて言えるのは、冷却面で大切なのはまずケースそのものだということです。
フロントからのエアフローをしっかり確保できる設計かどうか、これが何より決定的に重要です。
高性能なCPUクーラーも高効率なファンも、ケース内部の流れが悪ければ意味が半減してしまうからです。
ケースはまさに冷却システム全体を支える基盤であり、PCの安定稼働を裏で支える生命線なのです。
もっとも、外観や価格に惑わされるのも人間です。
見た目が美しいケースを選んで「これで十分だろう」と信じていました。
しかし熱でファンが常に全力で回り続け、作業がうるさくて集中できず、静かな環境で作業したいときに心底後悔したのを今でもはっきり覚えています。
静音性が失われた環境では、どれだけ高性能なPCでも快適性を支える力は激減します。
音に耐えきれず途中で投げ出した仕事さえあったのです。
さらに言うと、冷却不足は単なるうるささだけでなく生産性そのものを奪います。
ファンの音が常に耳にまとわりついて頭に内容が入ってこなかったり、動画編集のエンコードが途中で落ちてしまったりする。
そうした小さなストレスが積み重なると、長時間の作業は本当に苦痛になります。
この疲弊感は味わった人にしか分からないでしょう。
だからこそ、私は今では真っ先にケースに投資すべきだと強く思っています。
冷却性能に優れたケースを選べば、その結果として電力効率や騒音低減にも繋がります。
内部温度が低ければファンの回転数も抑えられ、システム全体の負荷も軽減する。
長期的に見れば電気代の節約にも繋がっていきます。
このようにケースの冷却設計にしっかり投資することは、一見地味ながら実際は生活の快適さに直結するものなのです。
見えない部分が最終的に大きな差を生むんです。
改めて考えると、私たちが何年も快適にPCを使い続けられるかどうかは、ケースの冷却にかかっています。
外観や一時的な満足感を追いかけるのも悪くはありませんが、数年にわたり安定してパフォーマンスを維持するためには冷却が欠かせない。
本当の意味で快適性を支えるのは見た目ではなく温度管理です。
私はその点で可能な限り妥協すべきではないと断言します。
最後にあえて強い言葉を残します。
冷却を軽んじたPCは必ず不満が残る。
反対に冷却を意識してケースを選んでおけば、長時間作業も安定して静かにこなせる。
2025年版 実際に試して良かったクリエイターPC構成ベスト5
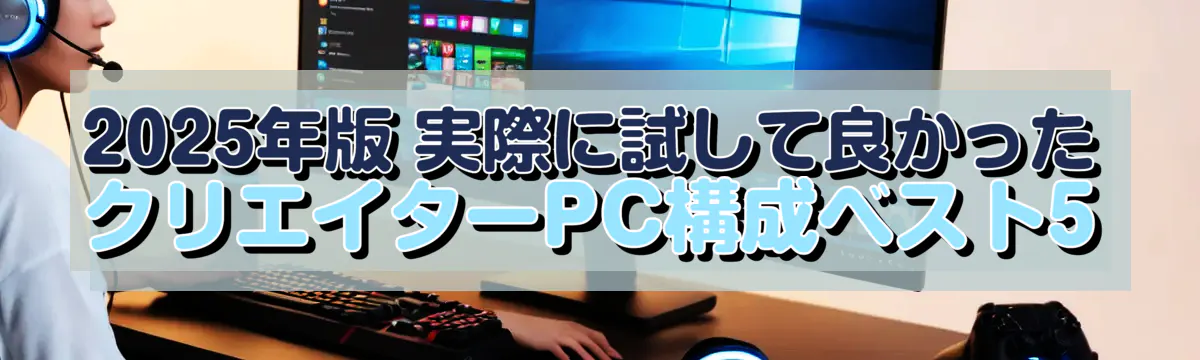
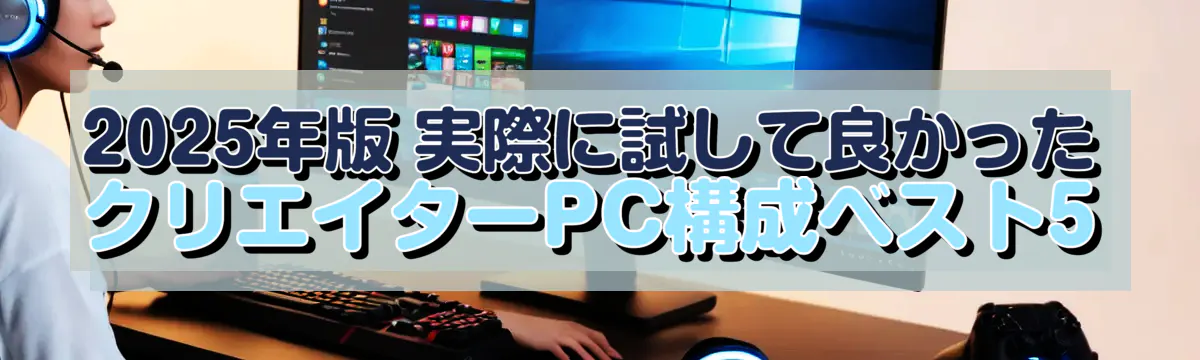
コストを抑えつつ使いやすい構成例
どこまでも性能を追い求めれば、財布の負担も果てしなく膨らみ、結局は使い切れない性能が眠ってしまう。
これはもったいないとしか言いようがありません。
私はこれまで何度も構成を試してきましたが、動画編集やイラスト制作、ちょっとした3D作業といった程度なら、ハイエンドは不要だと確信しています。
実際、中堅クラスのCPUとGPUで十分に快適にこなせるのです。
私が手を動かして組んだ構成は、Ryzen 5にRTX4060を組み合わせ、メモリは32GB、ストレージはNVMeの1TB SSDというものです。
使ってみると意外なほど軽快で、After Effectsで重い素材を扱っても処理落ちせず、プレビューもスムーズに流れる。
さらに驚いたのは、ファンが必要以上にうなりを上げることなく落ち着いて回っていた点でした。
長時間の作業でも電源が安定していて、途中で「大丈夫かな」と不安になることがありませんでした。
これが地味に嬉しいんです。
気付けば電気代も以前の構成より抑えられていて、小さな達成感すら感じましたね。
改めて思います、安心が一番大切なのだと。
もちろん人によっては「もう少し余裕が欲しい」と考え、RTX4070やその上を選ぶこともあるでしょう。
気持ちは分かります。
しかし私自身は、GPUを過剰に強化するよりも、メモリに投資する方が結果的に賢いと思っています。
Premiere ProでフルHD編集を行ったとき、16GBと32GBの差は体感として明らかで、作業中の待ち時間の長さがまるで別物のようでした。
書き出しを待ちながら「まだかよ…」と何度イライラしたことか。
ところがメモリを増設した途端、その待ち時間がぐっと減り、小さな苛立ちが嘘のようになくなったんです。
私は思いましたよ、ここをケチったら後悔しかしないなと。
パーツメーカーの選び方も意外と重要です。
私は何度か組み直した経験からASUSのマザーボードを選ぶことが多いのですが、その理由はシンプルでBIOSが分かりやすいからです。
余計な迷いがなく、設定の微調整もすぐ終わります。
一度MSIを試したことがあるのですが、そのときは小さな不具合に当たり、「あれ?何でこんな症状が出るんだ?」と首をひねった経験がありました。
それ以来、安定して使える安心感のあるメーカーを優先しています。
落ち着きが違うんですよ。
冷却に関しても誤解が多いように感じます。
初心者の方は水冷に強い憧れを抱きがちですが、実際は空冷で十分です。
特に中堅クラスのCPUなら大型の空冷ファンで静音性も確保でき、安定感も抜群です。
水冷のメンテナンスに不安を抱えるより、空冷で安心して作業できる方が結果的に満足感につながると私は思います。
先日、街中でゲーミングノートを開いて映像編集している若者を見かけました。
フットワークの軽さは魅力ですが、やはり冷却効率はデスクトップに敵いません。
自分は長時間落ち着いて作業したい人間なので、どうしてもノートよりデスクトップに戻ってしまう。
性分でしょうか。
では、最適な構成とはどんなものか。
私が導き出した答えはとてもシンプルです。
この組み合わせが、ほとんどのクリエイティブ作業を支える堅実な構成だと確信しています。
肝心なのは、高額なパーツを選ぶことではなく、自分の用途に合う性能を確保することなのです。
背伸びして買った高いパーツが埃をかぶるくらいなら、必要十分な機材の方が遥かに幸せになれます。
私自身、過去にハイエンド志向で大きな出費をし、後悔した経験があります。
購入直後は「もう不自由なんてない!」と意気込んでいたのに、半年も経たずにその大半の性能を使い切ることはなかった。
その体験から得た教訓は一つ。
性能の高さを誇るより、実際に普段使う作業がどれだけ快適にこなせるかが大事なのだということ。
だから私は今のミドルレンジ構成を胸を張っておすすめ出来ます。
余計な欲を出さない構成。
これこそが真の安心なのかもしれません。
結果として私は、数字やレビュー、他人の評価に振り回されることの無意味さを痛感しました。
自分の作業と真摯に向き合って、その中で必要な要素を見極めることが、最終的に最も合理的で満足感のある投資につながるのです。
ハードにかける費用だけでなく、自分の限られた時間を無駄にしないことにも直結します。
社会人として仕事や家庭の両立に追われる毎日の中で、納得できる構成を組めているという安心感は、想像以上に大きな支えになります。
だから私は声を大にして伝えたい。
派手さよりも堅実さ、安心感こそが最も価値のある選択だと。
動画編集に集中する人向けの構成例
正直に言うと、私は4K編集を真剣にやるなら迷わずGeForce RTX 4080以上のGPUを選ぶべきだと思っています。
無理に格好をつけたいわけではないのですが、処理の速さや安定感が桁違いなんです。
たとえば大量の素材を並べてもプレビューが途切れずに動くかどうかは、そのまま作業のストレス量に直結します。
以前、性能を抑えて妥協した機材で作業していたときは、画面が止まるたびに集中力を削られ、結果的に同じ場面だけで何度も同じ作業を繰り返すことになってしまい、「なぜ最初から投資しなかったのだろう」と後悔しました。
パーツへの投資は無駄ではなく、最後には確実に自分の時間と安心を取り戻してくれると、私は経験から強く思っています。
CPUに関しては、やはりCore i9-14900Kクラスが私には合っていました。
初めて導入して挑戦したのは、エフェクトを多用した大規模な編集作業でした。
数時間は覚悟していた書き出しが、驚くほど短い時間で終わってしまったのです。
そのとき本当に肩の力が抜けました。
クロマキー処理や複数トラックの同時再生も、まるで見えない手で作業を押し進めてもらっているように軽快で、ああ、これが高性能CPUを導入する意味なんだなと実感しました。
やっぱり違う。
心の底からそう思いました。
メモリについては、32GBの環境で編集していた頃を思い出すと、正直もう戻れません。
大規模なプロジェクトでソフトがカクつくたびに、イライラを抑えられなくなったものです。
ソフトが止まりかけるたびに溜息が出て、集中力も削がれる。
編集というのは発想の積み重ねですから、作業を遮られるとモチベーションまで奪われます。
64GBに増設してからは状況が一変しました。
作業中の不安が消え、さらに128GBにしたときには、心にゆとりがあるとこれほど作業が楽しくなるものかと感動しました。
余裕のある環境がどれだけ大切か、今ならはっきり断言できます。
ひとつはプロジェクト保存用、もうひとつはキャッシュや書き出し専用。
これだけで待ち時間が体感的に大幅に減り、作業全体が滑らかに流れていきます。
以前は保存や書き出しの待ち時間に時計を眺めては小さな不満を募らせていましたが、この構成にしてからは作業集中が途切れません。
無駄なストレスがなくなるだけで、こんなに変わるのかと感じました。
スピード感を維持できることこそ、編集という根気のいる作業における大きな鍵だと今では思っています。
最近導入したASUS製のマザーボードにはThunderboltポートが対応していたのですが、これが想像以上に便利でした。
高速ストレージをすぐに接続できるし、外部ディスプレイとの相性でも不安がない。
以前は外付け機器との接続に悩まされることも多く、動作不良に頭を抱えたことが何度もありました。
今ではその悩みが一掃され、スムーズに作業できる喜びがあります。
通勤で満員電車を避けて、偶然ガラガラの車両に乗れたときのような開放感です。
冷却も見過ごせません。
以前はレンダリング中に熱が高くなり、処理落ちして再度やり直すこともしばしばありましたが、今は静かで安定しています。
夜遅く作業していても冷却音が静かなので、余計な雑音に気を散らされることなく粛々と作業に打ち込める。
これは精神的にも非常に大きな違いでした。
ディスプレイも決して軽視してはいけません。
私はEIZOのカラーマネージメント対応モニターを導入したのですが、色再現性の高さから、自分の目が信用できるという大きな安心を得られました。
以前は納品直前に色味の違いを指摘され、徹夜で修正するはめになったことがあります。
それが今では完全に解消されました。
27インチをデュアルで並べる環境は、思っていた以上に快適で、タイムラインとエフェクトウィンドウを同時に広く見渡せる安定感は、一度慣れると手放せません。
集中力の質が根本的に変わるのです。
私が試行錯誤の末に選び抜いた構成をまとめると、RTX 4080以上のGPU、Core i9クラスのCPU、64GB以上のメモリ、NVMe SSD 2基構成、大型簡易水冷、そして正確な色を出せるディスプレイ。
この組み合わせが、日々の作業を大きく変えました。
昔感じていた「どうしてカクつくんだ」という小さな苛立ちは、今や遠い過去の記憶のようです。
余裕を持って環境を整えること。
それは効率だけではなく、自分の気持ちまで穏やかにしてくれると痛感しました。
頑張って工夫すれば何とかなる、ではなく、環境に余裕を作る。
私はこれを大人の選択だと思っています。
迷ったら性能を優先してください。
その選択は、必ず未来の自分に時間を返してくれる。
気持ちが楽になる。
そして最後に、自分の仕事に誇りを感じられる環境が整うのです。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EU


| 【ZEFT Z55EU スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DH


| 【ZEFT Z55DH スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster NR200P MAX |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55CM


| 【ZEFT Z55CM スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DR


| 【ZEFT Z55DR スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54H


| 【ZEFT Z54H スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
3DCGやレンダリング作業で頼れる構成例
理由のひとつは性能と消費電力のバランスで、これが作業の快適さを大きく左右するからです。
そうした無駄な不安から解放され、安定して作業を続けられることが、仕事道具としての確かな価値だと感じています。
毎日触るものですから、安心も欲しいですよね。
特に感じるのは、ビューポートを回転させたりパンしたりする動きです。
RTX4070ではそれが非常に快適で、ちょっとした操作にストレスを抱えずに済むのです。
以前は「ああ、また引っかかるな」と小さな苛立ちを積み重ねていましたが、それが解消されると創作の流れが途切れにくくなり、結果として仕事全体の効率に大きな違いが生まれます。
CUDAコアの数も十分なので、GPUレンダラーで試したときにきちんと時間短縮に繋がるのも魅力です。
これは机上の計算ではなく、目に見える時短となって現れてくれる。
そうすると自然と「選んで正解だったな」と心から思えます。
ただし、もし4K編集や大規模なレンダリングを日々こなすなら話は変わってきます。
数字のスペック差なんて、と内心軽く見ていた私自身が、使ってみて驚かされました。
建築パースの案件で複数の高解像度静止画を一気に出そうとしたとき、それまで一晩かけなければ終わらなかった処理が、たった3時間半ほどで納まったんです。
夜の時間がまるごと浮いて、翌日は別の仕事に手を付けられる。
そのリズムの変化に「環境を変える意味はここか」と頷かされました。
時間を奪われない快感。
ここは強調したいところです。
快適さの基盤。
メモリに関しては、64GB以上を本当に強く勧めます。
32GBで作業していた頃は、重いテクスチャやシミュレーションを扱うとすぐリソースの壁に突き当たり、締切間際にソフトが落ちて頭を抱えたこともありました。
あのときの焦りと絶望は正直トラウマです。
だからこそ64GBに増設したときの安心感は大きくて、心に余裕ができる分、作業にも集中できる。
必要なら128GBまで積んでも決して無駄ではないと今は実感しています。
ストレージの構成も侮れません。
システム用に2TBのPCIe Gen4 SSDを使い、作業用にさらに大容量のNVMe SSDを導入したときの変化は忘れられません。
Blenderで大規模なプロジェクトを開いた際、以前はロードだけで6分以上待たされていたのに、今では1分強で開くようになったのです。
最初の体験では「えっ、もう立ち上がったの?」と独り言が出てしまったほどでした。
この違いは一見小さいように思えても、積もり積もって制作全体の効率に直結します。
ちょっとした修正を思いついた瞬間に試せる、その軽快さが仕事の質を変えます。
最終的に求めるべき構成は明確です。
GPUは用途に応じたハイエンド、CPUは高クロックで多コアのモデル、メモリは64GB以上、ストレージはGen4世代で十分な余裕を確保する。
この4つをしっかり押さえるだけで、作業速度も品質も、そして心の余裕も大きく変わります。
納期に追われる不安から解き放たれ、もっとクリエイティブな部分に意識を振り向けられる。
これに投資する価値は疑いようがありません。
私はこれまで数十台のマシンを組み、試行錯誤しながら進んできました。
そのたびに痛感したことがあります。
「効率が上がることで変わるのは結果だけではなく、心の余裕も変えてくれる」ということです。
道具に投資するというのは、自分の心の健康と仕事の質に投資することでもあるのだと、40代になった今なら素直に言えるようになりました。
焦りから解放されたとき、人は思っている以上に柔軟になれる。
そうしてこそ、自分らしい表現や成果に辿り着けるのだと確信しています。
だから私は、この構成を自信を持って勧めるのです。
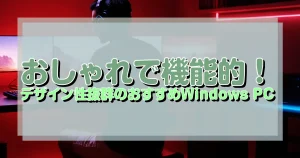
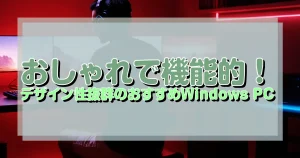
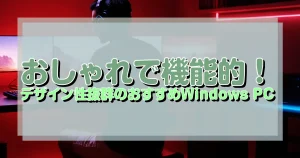
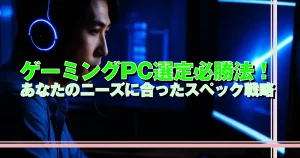
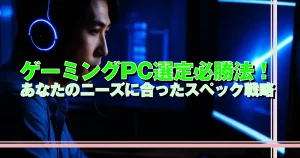
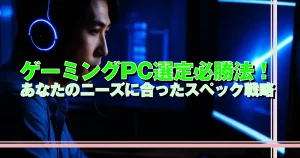
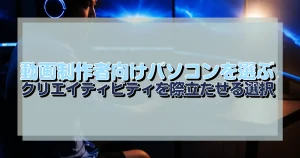
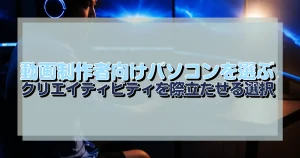
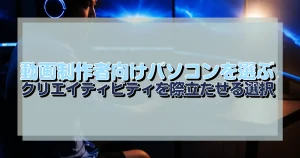
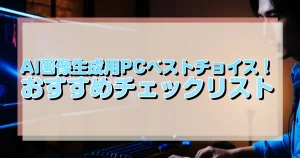
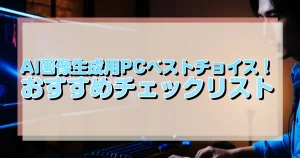
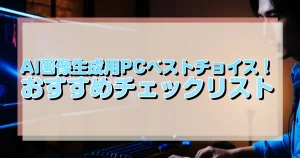
配信と編集を同時にこなす多用途構成例
配信と動画編集を同時に行う場合、安定した環境を整えることが何より大切だと痛感しています。
少しでも負荷が高まった瞬間に、音声が遅延してリスナーの耳を不快にしたり、画面がカクついて内容が伝わらなくなったりする。
そんな事態を経験したときの冷や汗は、今でもよく覚えています。
安定は裏方の仕事を支える土台、そう強く思うようになりました。
そこで私は自分の環境を一新し、Ryzen 9とRTX 4080 SUPERを軸とした構成を導入しました。
正直に言えば初めは半信半疑で、投資が本当に意味を持つのかと思っていました。
しかしいざ配信とDaVinci Resolveを同時に走らせてみると、GPUの使用率がおおむね50%前後で安定し、胸をなで下ろす瞬間があったのです。
余裕ある機材が気持ちの余裕へとそのままつながる。
これは机上の理屈ではなく、体験して初めて実感できることでした。
ストレージ面はさらに強く実感があります。
当初はNVMe SSDを1本だけで運用していましたが、キャッシュの処理が途端に詰まり、動画の読み書きで頻繁に引っかかる場面に悩まされました。
しかしシステム用と動画用に役割を分けてNVMe Gen4 SSDを2本導入した瞬間、状況は一変しました。
同じ作業なのに、まるで渋滞が一気に解消されたかのようにスムーズに進む。
実際の体感がここまで変わるとは想像していませんでした。
人間の小さな投資への迷いなど、効率の前では無意味に思えてくるほどだったのです。
メモリについても同じです。
私自身「32GBで十分だろう」とたかを括っていた時期がありましたが、思い切って64GBに増設したところ、配信中に動作が急に重くなるような不安定さはほとんど消えました。
配信というのは本質的に一発勝負。
フリーズすればそれで終わり、取り返しはつきません。
あの、画面がカタッと止まった瞬間の嫌な汗を、二度と味わいたくなかったのです。
だからこそ、メモリに追加コストをかけるのは結果的に「事故を防ぐ保険」でした。
これは数字では測れない安心に変わります。
必須です。
もう一つ忘れたくないのが電源ユニットです。
最初に自作した際、価格を優先し、安価な電源を使ったのですが、それが裏目となり、一度突然のシャットダウンを食らったことがあります。
その瞬間まで進めていた編集データはすべて消え、呆然と画面を見つめていました。
背筋が凍る、とはこういうことなのだと痛感しました。
その教訓から、私は今では850W以上、できればPlatinum認証を持つ電源を最低限と考えています。
それは単なる機材選びではなく、自分の仕事を守る保険のようなものなのです。
冷却についても人それぞれの判断があるでしょうが、私は静音性を強く求めています。
深夜に集中して作業しているとき、耳に入る騒音が少しでも大きいと驚くほど集中力が途切れます。
その体験から、冷却性能と静かさを両立できるモデルを選びました。
静寂の中でマシンが静かに動いてくれている、その心強さがどれだけ作業の疲れを減らしてくれるか。
これは数字では決して測れない効果です。
静かさが力になります。
最初は「これはやりすぎじゃないか」と心のどこかで思っていました。
しかし使い続けるうちに、この投資こそが無駄を省く最短経路であることを知りました。
「結局この方が安上がりだった」と気づいたとき、自分の過去の遠回りを少し悔やみました。
今の環境では、配信中に落ちる心配をする必要がなくなり、意識をすべて内容そのものに向けられるようになりました。
それが本当にやりたかったことです。
技術とは人を不安から解放し、創造へ背中を押すために存在するのだと、ようやく体で理解しました。
「妥協しない設備投資こそが一番の近道になる」と。
途中で繰り返した遠回りがあるからこそ、これから配信を始めたい、編集を本気で取り組みたいと考えている人には、最初から余裕ある構成を選んでほしい。
遅れて気づいた私だからこそ、切実に伝えたいのです。
最後にもう一度まとめます。
Ryzen 9やCore i9といった強力なCPU、RTX 4080以上のGPU、64GBのメモリ、2本のNVMe Gen4 SSD、そして堅牢な電源と静音冷却。
この組み合わせこそが、私自身が身をもって「安心しておすすめできる」と言える構成です。
この形にたどり着いたとき、私はようやく仕事と配信を本当に楽しめるようになりました。
安心できる環境。
静音性を重視して長時間作業に向く構成例
静かな環境で仕事を続けたいのであれば、水冷のような静音性を重視した冷却方式を検討する価値は高いと私は思っています。
特に映像制作や3Dのレンダリングといった重い処理を続けると、空冷ではファンが大きな音を立て、作業に入り込もうとする集中力を乱されます。
その点、水冷システムは安定して温度を抑えてくれて、夜遅くに自宅で作業をしていても家族の生活を邪魔しない静けさが得られます。
あの静寂を一度体験すると、戻れないんですよ。
昔、私が空冷でPCを自作していた頃を思い出します。
性能的には問題ないのですが、とにかくファンが全開になったときの騒音がひどく、まるで部屋の一角に古い掃除機が置かれているようでした。
テレビの音さえ負けてしまい、集中どころの話じゃなかったんです。
そんなとき、静音ファンで有名なNoctuaを導入してみたら、体感がガラリと変わりました。
数値的には10dB程度下がっただけでしたが、それ以上に静けさが身体に沁みてきて、「こんなに違うのか」と思わず一人で声に出してしまったのを、今でも忘れません。
集中できるかどうかって、実は小さな音の積み重ねに左右されるんです。
動画編集のように数時間ぶっ通しで作業をしていると、低い唸り音があるのとないのとでは疲労感がまったく違います。
音のストレスってジワジワ効いてくる。
静かだからこそ5時間、6時間と作業しても気が散らず、結果的に効率まで上がるんです。
そして仕事を終えたときの心の余裕も、やっぱり違うんです。
私がケースをFractal Design製に変えたときは、正直感動しました。
見えない場所に貼られている防音材の厚みや配置、空気の流れを邪魔しない工夫、細部まで「静かで長く付き合える」ことを考えて設計されているのを実感したんです。
そして見た目もすっきりしていて、仕事場の落ち着いた雰囲気に自然に馴染むんですよね。
要は派手にカスタマイズする必要はないということです。
CPUを冷やす簡易水冷ユニット、品質の高い静音ケース、そして低回転でも安定した風量を確保できるファン。
この最低限の組み合わせだけで充分意味があります。
あれこれ詰め込んで複雑にするより、シンプルに堅実に揃える方が、安心して長く使える構成になる。
40代になった今の私には、この「長く安心して付き合える」という感覚が、若いころよりずっと大切に思えるんです。
実際そうした構成にしてからというもの、長時間の動画編集を続けても耳が疲れないことに驚いています。
無音とまではいきませんが、気にならないレベルに落ちているおかげで「騒音に意識を割く」必要がなくなり、単純なことながらその効果は大きい。
静けさが、これほど作業効率を変えるとは思っていませんでした。
夜の机に向かう時。
気持ちが軽いんです。
仕事のノイズではなく、心地よい沈黙がそこにある。
パソコンはただの道具なのに、静かに支えてくれる相棒みたいに感じる。
こうなると、多少仕事が立て込んでも安心して取り組めるんですよね。
音が落ち着いていると、心まで穏やかになれる。
不思議ですけど本当なんです。
私の考えでは、冷却力を追い求めすぎて静音性を犠牲にする必要はないんです。
仕事で日常的に使うPCは、冷却と静音のバランスがとれているかどうかが一番大切です。
無理に高出力な装置を入れても、日々の生活の中ではオーバースペックになりがちですし、逆にストレス源になる。
派手さより落ち着き。
やっぱりここに尽きると思います。
長時間作業には静けさが必要です。
私はこの二つを欠かさず意識することが、ビジネスパーソンとして毎日の生産性を守るうえで欠かせないと考えています。
それは誇張でも理想論でもなく、私自身が実際に体感している事実です。
だからこれからも私は、静音性を基準にした選び方をずっと続けると思います。
そうして選んだ結果が、結局は自分の集中力や仕事の質に返ってきてくれると思うからです。
クリエイターPCについてよくある質問
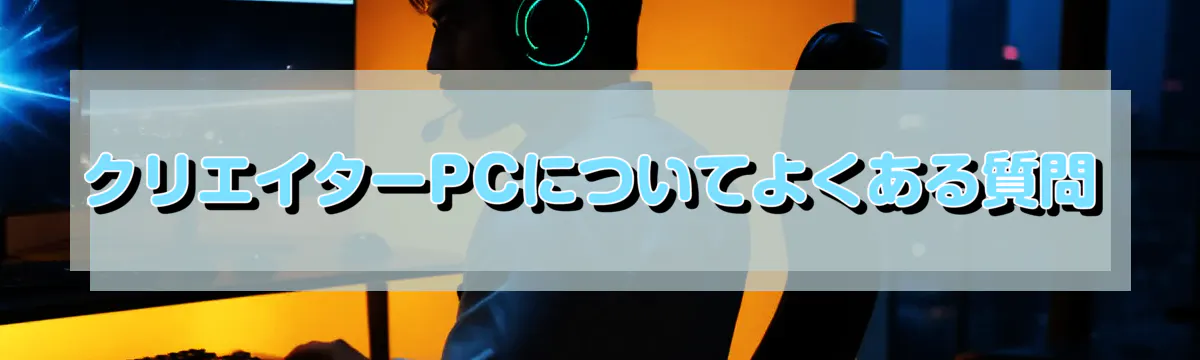
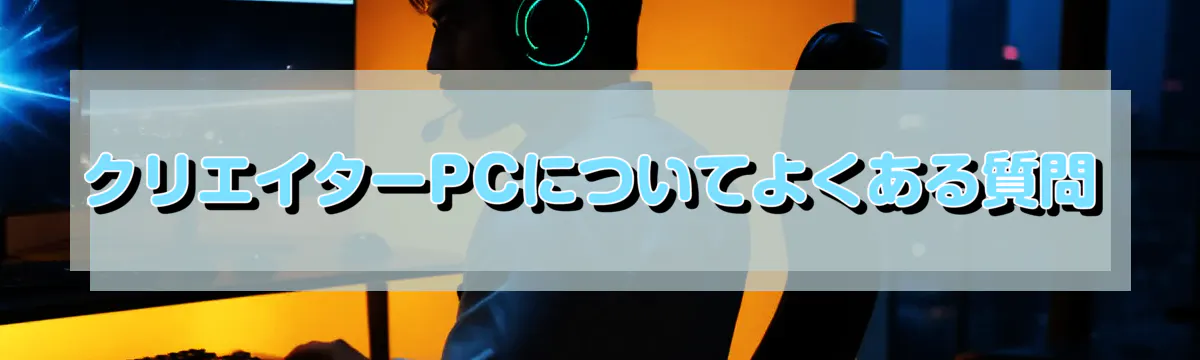
クリエイターPCとゲーミングPCの違いとは
クリエイターPCとゲーミングPC。
この二つは似ているようで実際は大きく異なる存在です。
私は両方を使ってきた経験から、それぞれの強みや限界を肌で感じてきました。
そして、その違いを知らずに高額な買い物をしてしまうと「どうも思ったように使いこなせないな」と後悔することになるのです。
以前、同僚に相談を受けたときもまさにその典型で、良かれと思って選んだPCが場面によって実力を発揮できない。
そんな現実を目の当たりにしました。
だからこそ、今日は私の実体験をベースに率直に書きたいと思います。
制作を仕事にしている人が選ぶべきは、正直に言うとクリエイターPCです。
動画編集や3Dモデリングなど長時間にわたる作業では、持久力と安定感がすべてを決めます。
例えば何時間も続く高負荷のレンダリングでは、一般的な構成だと熱や電力周りの設計が追いつかず処理が止まってしまうこともある。
しかし、クリエイターPCは専用設計のおかげで連続稼働でも安定する。
これは机に向かう身として「途中で止まるかもしれない」というストレスがなく、安心して背中を預けられる強さになります。
安心感ですね。
CPUとメモリの存在も決して軽視できないと私は考えています。
知人が得意げに見せたゲーミングPCで動画編集を試したとき、GPUは豪華なのにCPU性能が中程度で、エンコードが想像以上に遅かった記憶があります。
隣で「見た目だけじゃダメなんだなあ」と笑いながら作業を見守るしかなく、その瞬間に大切なのは派手さではなく全体の最適化なんだと実感しました。
一方、ゲーミングPCは考え方そのものがまるで別世界です。
求められるのはGPUの瞬発力であり、フレームレートの向上や滑らかな映像表現に直結します。
つまり発想がとてもシンプルで、「ゲームが気持ちよく楽しめれば勝ち」という目的に特化しているのです。
新作タイトルを起動したときの広がる景色、爆発シーンの迫力、その場で直接心を揺さぶられる瞬間があります。
こればかりは理屈抜きで体験した人にしか分からない興奮でしょう。
ただ、最近のGPUの進化には驚かされます。
NVIDIAの最新世代は圧倒的に高い処理能力を誇りますが、ゲームしかやらない人には正直オーバースペックに映ることもあるでしょう。
これはまさに「時間を短縮するためにお金を投資する」という働く大人にとって合理的な武器であり、生産性を押し上げてくれる無二の存在になるのです。
効率性という名の力です。
冷却の思想にも両者の違いが如実に表れます。
ゲーミング用は数時間のプレイを想定しているため、その範囲で熱を逃がせれば十分。
けれど制作の現場では、昼から夜まで止めずに回し続けるなんてよくある話です。
その状況で本領を発揮するには、ケースのエアフロー設計、電源供給の安定度、パーツ同士の相性まで神経質に整えられていなければならない。
私はこの点を強く意識するようになり、やっと両者が全く異なる設計思想で組み上げられていることに気づきました。
まったく別物。
では結局、どちらを買うのが正解なのかという疑問が浮かぶでしょう。
私の答えはこうです。
高いと思っても、取り戻せる効率と成果がその価値を証明してくれます。
一方で、ゲーム中心のライフスタイルを望むなら、ゲーミングPCで十分に幸せを感じられるはずです。
中身のパーツは似ていても、方向性の違いがこうまで結果に差を生み出すのかと、私は改めて感心しています。
私自身も若い頃は新しいパーツが出るたびに衝動買いして「最新こそ正義」などと浮かれていました。
ただ、40代に入った今は物事の選択基準がだいぶ変わりました。
「これは自分の生活にどんな価値を与えてくれるのか。
仕事にどんなプラスになるのか。
」そんな視点で冷静に判断するようになったのです。
見せびらかしではなく、一緒に日々を前に進める力。
必要なのはそういう確かな相棒です。
そして最終的な私の考えはシンプルです。
制作で実力を引き出したいならクリエイターPC。
娯楽に没入して楽しみたいならゲーミングPC。
同じ高性能というラベルが貼られていても、その裏に隠された物語はまるで違います。
選び間違えなければ、どちらも最高のパートナーになれるのです。
信頼できる存在。
結局、自分がどう生きたいのか、どんな時間を大事にしたいのか、その問いに対する答えがPC選びに直結しているような気がします。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
クリエイターPCはBTOと自作どちらが選びやすいか
まず何より、届いたその日からすぐ実務に使える安心感が大きいのです。
余計な初期設定や相性問題に悩まされず、本業に集中できることのメリットは、私のように納期に追われる仕事をしている人間にとって計り知れません。
映像制作やデザインの現場では、数時間の遅れがそのまま信用問題につながることもあります。
だからこそ、費用が多少高くついたとしても、メーカー保証やサポート付きのBTOを選ぶことが、結局は最も現実的で賢明な投資になると私は実感しています。
GPUやストレージを自分好みにカスタマイズし、ケースの冷却性能まで徹底的に吟味する時間は楽しいものでしたし、完成したときには「これぞ自分だけの一台だ」と気分が高揚しました。
でもその一方で、BIOS調整やドライバの不具合と格闘することになり、深夜に何度も心が折れそうになった記憶があります。
自作は確かに自由ですが、その自由を扱うには覚悟が必要だと痛感しました。
あのときのことは今でもはっきり覚えています。
映像編集で動作検証を兼ねつつ自作に挑戦し、思い切って最新のGPUを導入したのですが、レンダリング中に突如としてエラーが出て真っ青になった夜がありました。
その翌朝には重要な案件の納品が迫っていたので、もう心臓が破裂するんじゃないかと思ったほどです。
必死に祈るような気持ちで徹夜作業をし、画面が無事最後までレンダリングを終えた瞬間は泣きそうなくらい安堵しましたね。
便利さや性能を超えて、自分自身の精神力まで試されるのが自作だと、その夜ほど身にしみて実感したことはありません。
怖さと魅力が同居する経験でした。
一方で、BTOであれば話は全く違います。
納期が明確に設定されており、トラブルが起きても問い合わせ先がすぐ分かる安心感があります。
これは私たちビジネスパーソンにとって、本当にありがたい仕組みです。
仕事は一分一秒を争うことも多く、PCトラブルに飲み込まれて夜を無駄にする余裕なんてありません。
安定稼働こそ最大の価値。
この一点に尽きます。
頼りになる道具を手元に置き、心置きなく仕事に取り組めることほどありがたいものはないのです。
とはいえ、ここ数年の自作用パーツの進化には目を見張るものがあります。
発熱や消費電力の効率が飛躍的に改善され、小型のケースでも驚くようなパフォーマンスが発揮できる時代になりました。
昔なら大きなタワー型を前提に組んでいたハイスペック構成が、今では机の下に収まってしまう。
冷却や省電力技術がここまで革新を遂げていることは、正直感心せざるを得ません。
この流れがさらに加速すれば、自作というスタイルが再び大きな注目を浴びてもおかしくないでしょう。
ワクワクしますよね、正直。
それでも、私が仲間に勧めるのはやはりBTOなのです。
なぜなら、すぐに仕事に取りかかれる環境を整えることが私にとって何より重要だからです。
道具を安定して稼働させる、この点は妥協できません。
実務においては「動いて当たり前」が大前提であり、この信頼を揺るがす要素は排除するしかないのです。
特に私の年代のビジネスパーソンにとっては、気力も体力も限られている中で効率を最大化することが重要であり、そのためにBTOは最適解になるのです。
もちろん、自作ならではの達成感や「自分だけの一台を作り上げた」という満足感は、他では得られない大きな喜びです。
完成した瞬間のあの高揚感や、動いたときの感動は代えがたい経験です。
もし余裕があり、多少のトラブルすら楽しめる精神的なタフさがあるなら、チャレンジする価値は大いにあります。
ただ、私自身は毎日の納期や打ち合わせに追われていて、その余裕を持ち切れないのが現実です。
だからこそ迷わず私はBTOを選びます。
安定を優先するならBTO。
自由や挑戦を楽しむなら自作。
この二つの選択肢にきれいに分かれます。
私は迷う必要がない。
すでに自分の中で結論は決まっています。
これからPCを検討する仲間に断言できるのは、クリエイターPCを選ぶならBTOこそ最も現実的で安心できる手段だ、ということです。
信頼できる相棒。
モニターや周辺機器を選ぶときの基本ポイント
大げさに聞こえるかもしれませんが「機材を変えただけで、ここまで仕事の質が変わるのか」と思い知らされる体験をしてきました。
私自身、20年近くさまざまなデバイスを導入しては試行錯誤を繰り返し、失敗と後悔も数え切れないほど積み重ねてきましたが、ようやく「これなら安心して腰を落ち着けられる」と思える形に行き着いたという実感があります。
まず最重要なのはモニターです。
4Kの作業領域は、本当に広々としていて気持ちがいいんです。
以前はフルHD環境で作業していた時期もあり、動画編集のときに頻繁にウィンドウを切り替えてはイライラしていました。
つまり、効率が格段に上がったということです。
毎日のことだから、小さな効率化が積み重なって大きな違いになるんですよ。
さらに色の正確さ。
昔の私は「色なんてそれなりに合ってれば大丈夫だろう」と正直なところ思っていました。
けれどEIZOのCGシリーズモニターを導入した瞬間、まるで眼鏡を初めてかけたときのような衝撃を受けました。
今まで「まあこんなものか」と見逃していた色のズレがはっきり見えてしまい、初めて本気で映像と向き合わなければならないと痛感したんです。
あのときのショックは今でも忘れません。
プロとしてこの部分を軽視したら、後で必ず後悔する。
入力デバイスも無視できません。
キーボードはただの文字入力の道具ではなく、一日の大半を共にする相棒です。
まさに武器になったという感覚ですね。
一度この快適さを味わったら、もう安価なキーボードには戻れなくなります。
それからマウス。
これも侮れません。
人間工学的な説明も大切ですが、最終的には感覚としてしっくり来るかどうか。
次に外付けSSD。
まだHDDだけでやりくりしている人を見ると、「いや、それはもったいない」とつい声をかけたくなります。
私はSamsung製のポータブルSSDを導入しましたが、その転送速度には笑ってしまいました。
大容量のデータを移す場面では、一秒の違いが積み重なって疲労感や集中力に直結します。
速さは正義。
この事実を実感しました。
そして盲点になりやすいのが音です。
正直に言えば、昔の私はスピーカーよりまずモニターや入力デバイスに予算を回したいと思っていました。
しかし、あるときスピーカーを導入してから世界が変わりました。
ヘッドホンだけでは把握できなかった音の広がり、低音の厚み、定位のバランス。
それらが一気に分かるようになったのです。
小さな投資で大きな効果。
これを身をもって体験したのです。
その積み重ねが後のスピードと安心感につながるのです。
環境整備とは一度で終わるものではなく、日々の試行錯誤でブラッシュアップしていくもの。
年齢を重ね、体力が無限ではないと感じる今だからこそ、その意味が胸に響きます。
最も重要なのは快適さと効率のバランスです。
4Kの視認性で作業をしやすくし、高色域のモニターで色のブレを防ぐ。
SSDでストレージの不安を消し、キーボードとマウスで操作性を磨き、スピーカーで音を正確に把握する。
その結果として、毎日の「なんとなくしんどいな」という感覚が驚くほど減ります。
安心感。
それはお金以上の価値を持つもので、心を穏やかにしてくれる存在です。
私が若いクリエイターにアドバイスするとしたら、こう伝えます。
数百時間、数千時間を費やす環境で、その投資の差は結果に確実に反映されるからです。
快適な作業環境は、効率のためであると同時に、自分の心を守るための投資でもあります。
私はこのことを、何度も失敗し、少しずつ改善を繰り返す中で痛感してきました。
これは机上の空論ではなく、私が体で覚えてきた揺るぎない実感です。