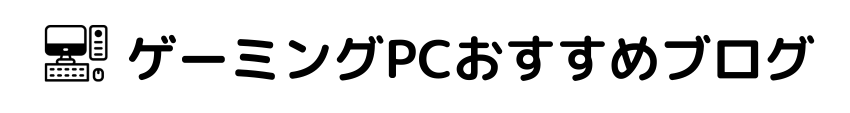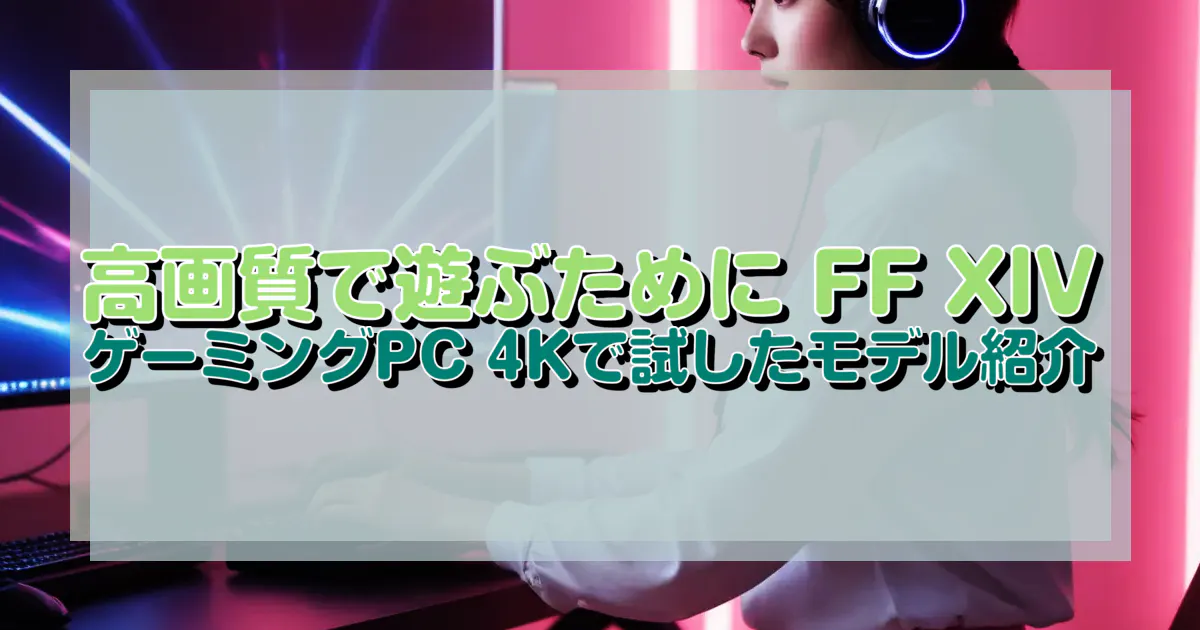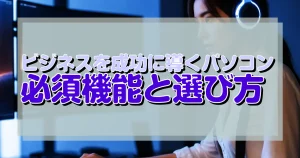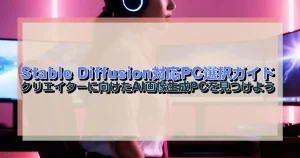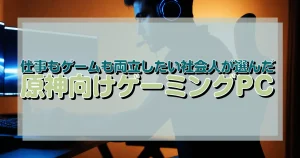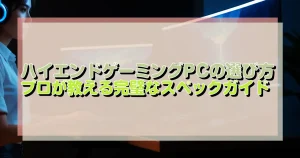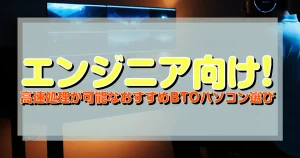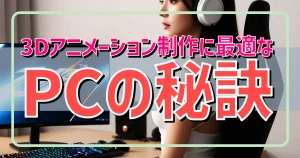FF XIVを4Kで楽しむために実際に必要なPCスペックをチェック
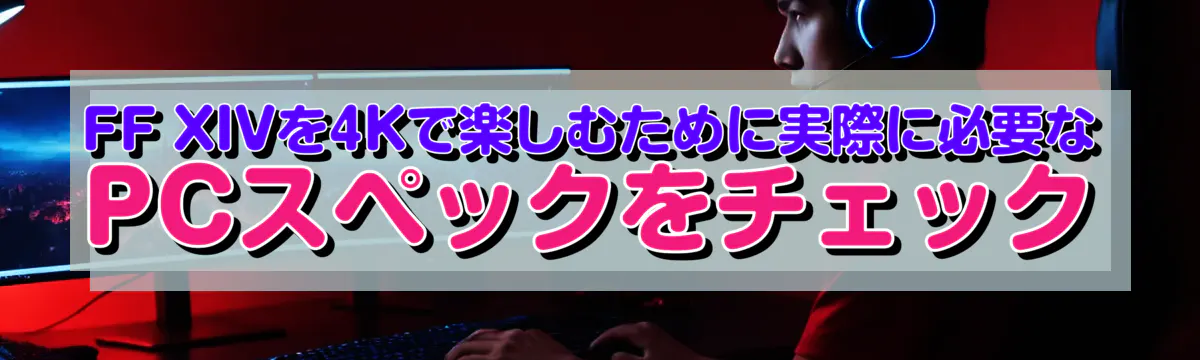
CPUはインテル派とAMD派、それぞれの使い心地を比べてみる
実際に自分でインテルとAMDのCPUを両方試してみると、その違いは机上の比較以上に明確でした。
そして正直なところ、どちらを選ぶかでゲームや作業の心地よさは大きく変わるのです。
私は最初、数字やベンチマークだけで結論を出そうとしましたが、それでは見えてこないものがありました。
体感としての速さや安定感、そこから得られる安心が日常の中でどれほど大きいかを、身をもって知ったのです。
結局のところ、CPU選びはカタログスペックよりも実際の経験に重きを置くべきだと感じました。
インテルを使ったときにまず驚いたのは、パソコンの起動から操作までが非常に軽快だということでした。
大勢のプレイヤーが集まるゲーム内の都市部でもフレームが落ちにくい姿には「これだよ」と思わせる力がありました。
数字では示せない安心感。
私には、その挙動がまるで優秀な同僚が淡々とタスクを片付けていく姿のように映り、素直に感心しました。
いや、正直うらやましさすら感じましたね。
一方で、AMDは長丁場に強い。
特に3D V-Cache搭載モデルを試したときの印象は今でも鮮明です。
派手な演出や大人数のレイド戦など、CPUに大きな負荷がかかる場面でも揺らがない。
長時間プレイしても温度上昇が緩やかで、ファンがうるさくならないこともあって、夜更けのプレイでも静かに集中できました。
まるで古くからの友人がそっと支えてくれるような、そんな温かさすら感じたのです。
これは数字では測れない実感でした。
操作の速さや切り替えの滑らかさに関してはインテルの優位が目立ちました。
仕事で動画を編集中、タイムラインを素早く行き来するときに引っかかりがなく動くこと。
これがどれほどストレスを減らしてくれるか、日常的に触る人間であればすぐ理解できます。
ほんの少しの差に見えても、それが積み重なると大きな快適さとなる。
私はそこで改めて技術の細部が生活の質を確実に変えることを思い知らされました。
ただし、夜中まで熱中してゲームを続けるシーンではAMDの存在がありがたかったです。
どれほど長く遊んでもCPUの温度が穏やかで、耳をつんざくファンの騒音に悩まされない。
それは、気がつけば自分の時間を邪魔されずに純粋に楽しめているということ。
孤独な時間を静かに守ってくれる存在だと、本当に思いました。
そしてその時「パフォーマンスとは数字だけでは表せない」と呟いてしまいました。
この棲み分けが実に興味深いのです。
インテルは瞬時の応答が必要な場面で活躍し、AMDは腰を据えた作業や長時間のゲームにうってつけ。
まるでチームを支えるエースとリリーフ投手の関係。
そのバランスこそが重要だと納得している自分がいて、思わず笑ってしまいました。
コスト面を見ても、インテルのミドルハイ帯には実力とバランスを兼ね備えたモデルが揃っていました。
私が検討したCore Ultra 7 265Kは、介在する無駄が少なく、実務でもゲームでも安心して任せられる万能型。
仕事の資料を処理しながら、そのまま高解像度の最新ゲームも快適に遊べてしまう。
正直、「これ一つあれば困らないな」と思わされました。
AMDではRyzen 7 9800X3Dが特に印象的でした。
重たい処理でも無駄に熱を上げず、ぶれずに安定したパフォーマンスを出し続ける姿勢。
長時間FF XIVを動かした後も「あれ、まだ余裕があるな」と感じられたのは強い信頼を抱く瞬間でした。
最初はそこまで体感差があるとは想像していませんでしたが、毎日継続して使うと細部に息づく違いがじわじわと効いてくるものです。
感覚というのは侮れないとつくづく感じました。
では最終的にどちらを選ぶのが良いのか。
明確に言えるのは、自分の使い方をどう考えるかに尽きるということです。
重たいレイド戦や最高設定での討伐を徹底的に楽しみたいならAMDのRyzen 7 9800X3Dが向いています。
一方で、普段の仕事にも遊びにもバランスよく対応し、快適なレスポンスを求めるならインテルのCore Ultra 7 265Kが安心です。
つまり選び方の基準は「自分がどんな時間を過ごしたいか」という一点なのです。
この判断は、単なる技術の選択ではありません。
時間の限られた大人の趣味と仕事をどう両立させたいのかを映す鏡のようなものです。
CPU選びに妥協すると結局のところ、自分の生活そのものに小さな不満が積み重なっていく。
私はそこで学びました。
大切なのはスペックではなく、自分の時間を守れるかどうかだと。
だからこそ、今後CPUを選ぶ際には人によって「答え」が必ず異なるのだと思います。
快適さを選ぶのか。
最後は、自分自身の生活スタイルを考えるしかありません。
私にとってこの選択は、自分の生き方や働き方を問い直すことでもありました。
選ぶものによって日々の快適さが変わる事実を忘れず、自分の時間をどう使うかを大切にしてほしい。
ただし、自分に合った答えを見つけ出すこと。
それこそが最大の満足につながると、私は声を大にして伝えたいのです。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43074 | 2458 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42828 | 2262 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41859 | 2253 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41151 | 2351 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38618 | 2072 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38542 | 2043 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37307 | 2349 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37307 | 2349 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35677 | 2191 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35536 | 2228 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33786 | 2202 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32927 | 2231 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32559 | 2096 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32448 | 2187 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29276 | 2034 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28562 | 2150 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28562 | 2150 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25469 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25469 | 2169 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23103 | 2206 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23091 | 2086 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20871 | 1854 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19520 | 1932 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17744 | 1811 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16057 | 1773 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15299 | 1976 | 公式 | 価格 |
今買うならどのGPUがコスパ的に現実的なのか
今の私の率直な結論を述べると、4K環境でFF XIVを安定して快適に遊ぶために、ハイエンドのGPUを購入する必要はないと思います。
必要以上にスペックを追い求めるよりも、中位クラスのモデルで十分満足できる体験が得られますし、その方が費用面でも精神面でもずっと健全だと感じるのです。
仕事を抱え、家庭もあり、限られた時間を趣味に使う私のような世代には、現実的で無理のない選択が最も重要だと改めて思い知らされました。
先日、試しにRTX5070Tiを搭載したBTOマシンを触る機会がありました。
フルHDやWQHDはもちろんのこと、4Kに設定しても快適に動作しました。
驚いたのは、大規模なレイド戦や都市エリアでもコマ落ちがほぼなかったことです。
昔なら「もっと上が欲しい」と思ったかもしれませんが、今の私は心の中で「これで十分じゃないか」と呟いていました。
いや、正直に言えば、もう十分すぎるほど快適でしたね。
ハイエンドモデルであるRTX5080を試した時、その滑らかさが一段上だと感じたのも事実です。
数字の上では確かに差があるけれど、体感で得られる満足度は価格差ほどではない。
私の財布を開くのは私自身であり、その重みをどこに配分するかは生活と直結しているわけです。
SSDを増設する、安定した電源を導入する、騒音を抑える冷却パーツを整える。
そのほうが私にとっては価値の高い投資でした。
現実的な選択はいつも冷静にコストバランスを考えること。
また、RadeonのRX9070XTという選択肢も侮れません。
実を言えば私は長い間、Radeonに少し苦手意識がありました。
昔は「色合いにクセがある」という印象が強く、あまり手を出さなかったのです。
しかし、最新のRX9070XTを実際に体験してみて、その固定概念は完全に覆されました。
自然で鮮やかな発色、長時間遊んでも目が疲れにくい快適さ、さらにFSR4によるフレーム補完が思った以上に高精度です。
場面によってはGeForceの同価格帯と肩を並べるどころか、むしろ上回る場合すらある。
正直、これは予想外でしたね。
価格も重要です。
しかし、5070TiやRX9070XTを中心に構成すれば、20万円前後で十分に高性能な環境が整います。
電源も750W程度で安定し、排熱や騒音も抑えられる。
無理をしなくても良いんです。
私たちの世代は、仕事が忙しく疲れて帰ってきてからやっと趣味の時間を楽しめる、そんな日常を送っています。
ですから、PC環境に余計な不安や悩みを抱えたくありません。
冷却が不安定で落ちるとか、電源が相性を起こすとか、そんなのにいちいち振り回される暇はないんですよ。
FF XIVのように仲間と語らいながら楽しむオンラインゲームなら尚更です。
ガチガチに勝ちを目指すFPSならまだしも、心地よく繋がる時間が欲しいんです。
こればかりは、数字では測れない安心感でした。
そうはいっても、もし8K解像度や240Hzといった極端な環境を目指すなら話は別です。
その場合は5080や5090といった最上位が必要になるでしょう。
ただし、それを本当に必要とするプレイヤーはごく一部だと私は考えています。
大多数の人が求めるのは、平均fpsの高さではなく、最低fpsの安定。
そこに尽きるのです。
やっぱり、無理をしても長く続きません。
私が一番強調して伝えたいのは、日常的な快適さの価値です。
表上のベンチマークスコアや最高性能を誇る数値ではなく、毎日のように感じる「ストレスの少なさ」こそが真の満足を生むということです。
そして余剰の予算をストレージやメモリに投じれば、今後大型化していくゲームタイトルにも対応できる。
これこそが現実的な強みになります。
120fpsが出るか出ないかに一喜一憂するより、安定して100fps前後を維持できる環境で気分よく仲間と遊ぶほうが、私にとってはよほど価値がある。
そういう年齢に差し掛かったのだと思います。
だからこそ、私が現時点で勧めるのはRTX5070TiかRX9070XTです。
中位モデルこそが、この時代において一番賢く安心できる選択だと自信を持って言えます。
価格も抑えられ、性能も十分、そして安定感に優れる。
三拍子揃った選択肢。
それだけで、日常のゲームライフは驚くほど楽しく、豊かな時間になります。
もう無理して背伸びをする必要はありません。
これこそが私にとっての正解だと、今ははっきり言えるのです。
安心感。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48704 | 101609 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32159 | 77824 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30160 | 66547 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30083 | 73191 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27170 | 68709 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26513 | 60047 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21956 | 56619 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19925 | 50322 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16565 | 39246 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15998 | 38078 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15861 | 37856 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14643 | 34808 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13747 | 30761 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13206 | 32257 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10825 | 31641 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10654 | 28494 | 115W | 公式 | 価格 |
DDR5メモリは32GBが妥当?16GBとの差を体感で検証
私はここ数年オンラインゲームを続けていますが、その中で自分の環境をどう整えるべきかについて本当に身をもって学ばされました。
特にFF XIVを4K環境で快適に遊ぼうとすると、やはりDDR5メモリを32GBにしておくべきだと強く思います。
16GBでもある程度は動きますし、ソロでのクエストや風景を眺めるだけならそこまで不自由を感じないこともありました。
しかし同時にブラウザを開いて攻略サイトを見たり、仲間とDiscordで通話を続けながら動画を流したりすると、とたんに重さが気になり、時折カクッと止まる瞬間にイライラするのです。
小さなつまずきのように思えても、その違和感は確実に積み重なり、気持ちよく遊ぶ時間を少しずつ削っていきます。
その一方で、32GBに切り替えた瞬間から私の印象はがらっと変わりました。
同じように複数アプリを立ち上げながらプレイしても、まったくブレない動作。
大人数でのコンテンツに突入したとき、画面上に無数のキャラクターと派手なエフェクトが舞おうとも、映像はきれいに滑らかに流れ続ける。
あの安定感が与えてくれる安心は何よりも大きく、ただの快適さ以上に「もっと遊びたい」という気持ちを後押ししてくれるのです。
まさに別世界。
16GB環境との一番の違いは、数字に表れにくい部分にありました。
ベンチマークのスコアだけを眺めると差は数%しか出ないこともあります。
ですが実際に長時間遊んでみると、そのわずかな差が大きな気持ちの変化を生み、快適さを左右するのです。
例えば人の多い街中でキャラクターが入り乱れているときに視点をくるくる回すと、16GBではどうしても反応が重くなる瞬間がありました。
あのストレスですよ。
以前の私は「まだ16GBで十分だろう」と本気で思っていました。
実際に1年ほどは16GBで使い続けて大きな不満を感じていなかったのです。
しかし32GBへ換装したその瞬間、心底思い知らされました。
「これは全然違う」と。
仕事でPCを酷使する立場としても、こうした余力が実際の安心感につながると肌で実感しました。
正直に言えば「もっと早く変えておけばよかった」と悔しさまでこみ上げてきました。
加えて昨年導入された拡張パッケージ「黄金のレガシー」によって状況は一層シビアになりました。
高解像度のテクスチャや光の表現などの演出がさらに強化され、負荷は確実に重くなっています。
16GBでも動作はしますが、遊んでいると細かなラグを体感するようになり、「これから続く新しい要素にこの環境だと追いつけるだろうか」と不安を覚えるのです。
使っていてはっきり分かるのは、メモリに余裕がないと一瞬で操作感が落ちてしまうということ。
そのことに気づいてからは、もう元に戻ろうとは考えられませんでした。
だからこそ私の答えははっきりしています。
ただそれだけです。
新しいグラフィックや演出が追加されるたびに必要とされる負荷は高まり、その壁はあっという間に目の前に立ちはだかります。
もし過去の自分に会えるなら間違いなく耳元で言います。
「遠回りはやめろ、早く32GBへ行け」と。
もちろん「コストが気になる」という声も耳にします。
確かにDDR5メモリが登場したころは価格が高く、気軽に導入できるものではありませんでした。
けれど最近は価格も落ち着き、BTOパソコンの標準構成でも32GBが選ばれるケースが増えています。
店頭で16GB構成を見ると、今ではどうにも心許なく映るのが正直なところです。
結局のところ、いずれアップグレードするのなら最初から32GBを選んだ方が結果的に満足度は高い。
そう感じています。
重要なのは「後悔しない選択」をすることだと思います。
その気持ちを支えてくれるのが32GBの環境です。
特に長時間プレイする方や、新作コンテンツを逃さずに遊びたい方ならなおさらお勧めできます。
安定した環境があるだけで、ゲーム体験の満足度は一段も二段も上がるのです。
最後にもう一度だけ強くお伝えしたいです。
FF XIVを4Kで心置きなく楽しみたい。
その願いがあるのなら、32GBを選んでおくべきです。
安心して続けられる環境。
なぜかと言えば、これからのアップデートや拡張を受け止めるには余力が必要だからです。
そしてその余力こそが、私たちが落ち着いた気持ちで長く遊び続けられる土台になるのです。
私はその選択が未来の自分を必ず助けると信じています。
NVMe SSDは容量2TBを選ぶと何が快適なのか
これまで1TBのSSDを使ってきて、何度も「容量が足りない」という壁にぶつかり、その度にインストール済みのデータを削除してやり繰りする羽目になりました。
仕事から疲れて帰ってきて、少しの自由時間くらい気持ちよく遊びたいのに、最初の作業が「データ整理」では気持ちが冷めてしまいますよね。
そういう面倒から解放された今の環境は、本当にありがたいとしみじみ思っています。
特に大型パッチの後が厄介でした。
数十GBも一気に増えるデータを目にすると、空き容量の残りを見ながら整理に追われる自分がいました。
なんとかインストールできたとしても、どこかで「また足りなくなるのではないか」とビクビクしてしまう。
正直、整理をしてようやく起動した頃にはもうゲームをする気力が半分削がれている自分もいたんです。
平日の夜、たった1時間でも自由な時間をつくることがどれほど難しいか、40代になって改めて痛感しました。
だからこそ、ここで無駄な労力をかけるのはあまりに惜しいと思ったんです。
ロード時間の問題も見逃せません。
数値で示される理論値は1TBでも2TBでも大きな違いはないと説明されます。
でも実際は残り容量に余裕を持っているかどうかで挙動が変わるように感じています。
特に人が多い都市部での動作は、2TBに換えてから明らかにスムーズになりました。
わずか数秒の違いと思うかもしれませんが、毎日積み重なるその数秒が「ストレスを溜めない」という点で大きな効果を発揮するんです。
待たされない。
これが想像以上に大きな価値だと実感しています。
そして動画保存の問題。
私は昔からプレイ動画をよく撮るのですが、4K録画ともなると数十GBなんて一瞬で飛んでいきます。
気付けば数本で数百GB。
それが1TBのSSDで起きると「残しておくべきか、捨てるべきか」の悩みがついて回るんです。
正直、ゲームを楽しむための動画を撮っているのに、自分でその価値を削るような選択を迫られるのは嫌で仕方ありませんでした。
しかし2TBにしてからは余裕があるので、とりあえず残しておく。
あとで見返したくなったらすぐ取り出せる安心感。
これがものすごく大きな変化でした。
最近のSSD事情を見ても、今主流のGen.4 NVMe SSDが持つ速度はすでに十分です。
5000?7000MB/sなんて数字を聞いても、正直私は専門家のような理解はできません。
でも実際に使ってみると「速い」と素直に感じられるわかりやすさがあります。
もちろん最新のGen.5対応もありますが、価格がグッと上がり、しかも発熱や安定性に配慮するコストも負担になります。
それを考えると、安心して使えるGen.4の2TBが今のバランスとしてちょうどいいと心から思います。
落ち着いて遊べる安定感。
これに尽きるのです。
でも実際には、インストールできるタイトルに限度があり「どうせ全部遊ぶのは無理だ」と諦め気味になっていたんです。
ところが今は違います。
気になる大型タイトルを入れっぱなしにしておき、好きなときに切り替えて遊ぶ自由を手にできました。
この広がりは想像以上に大きかった。
選択の余裕こそが遊び方の幅を広げてくれるんだと、ようやく実感しました。
だからもうそんなことで煩わされるのは嫌だ。
遊ぶなら遊ぶことだけ考えていたい。
こうして好きなときにゲームの世界へ飛び込める環境こそが、私にとって最大の魅力です。
だから2TBを選んだことは間違いではなかったと、今はっきり言えます。
もちろん、すべての人に2TBが必須だとは思いません。
普段から限られた作品しか遊ばない方なら、1TBでも事足りるでしょう。
ただしFF XIVのように定期的な大規模アップデートがあるタイトルを長く続ける人や、映像を残して楽しみたい人にとっては、容量に余裕があることが遊びの快適さを大きく変えてくれるはずです。
「データを消そうか」と一度でも悩まされるストレスから解放される。
これがどれだけありがたいことか、私自身の体験から強く感じています。
私はBTOショップで構成を考える際、最後まで1TBと2TBで迷いました。
価格差があることはもちろん理解していましたし、手が届く範囲で済ませようかと心が揺れたんです。
でもそのときに思い出したのは、以前の窮屈な体験でした。
「あの面倒をもう一度やりたいか?」と心に問いかけた時、答えはすぐに出ました。
もう後悔はしたくない。
だから2TBを選んだんです。
私は今、その判断が正しかったと胸を張って言えます。
結局どう選ぶか。
私の答えは一つに絞られます。
2TBを選ぶこと。
それが容量の余裕、そして心の余裕につながり、遊ぶ楽しさをさらに広げてくれるからです。
安心できる環境を手に入れるなら、迷う理由はないと私は信じています。
これが私の実感です。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
自分で用意したFF XIV用ゲーミングPCのテスト結果レポート
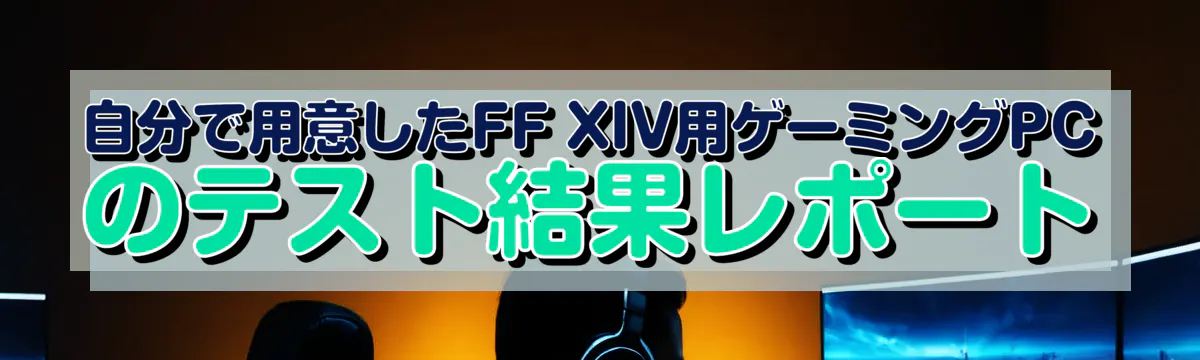
RTX 5070Tiを積んだ構成で実際に4Kプレイしてみた感想
フルHDやWQHDの環境では正直不満はなかったのですが、4Kは贅沢だとどこかで思い込んでいたのです。
しかし、いざ導入するとその先入観は完全に崩れてしまいました。
人がひしめく都市部でも24人レイドのような重い場面でも、描画が不自然に落ちることなくスムーズに動き続け、プレイを邪魔するカクつきがないのです。
プレイヤーとしてはそれがどれほど大きなストレス軽減につながるか、身をもって実感しました。
コンピュータの技術ってここまで来たのかと、胸の中で思わず唸ったほどです。
グラフィック表現に関しても、本当に衝撃を受けました。
水面に映る光がただのグラフィック上の反射ではなく、まるで実際の湖や川を覗き込んでいるように自然なのです。
街並みに差し込む光と影が重なり合う様子も、ただ綺麗という言葉では片づけられない味わいがありました。
風でなびく草木の影が画面全体に広がり、それが時間の経過や天候の変化と絡み合う。
こうした細部の積み重ねが、ゲームの世界を本当にそこに存在しているかのように錯覚させてくれるのだと思いました。
自分のキャラクターが装備する鎧の質感や剣に走る光沢の再現力にも驚きましたし、魔法の光が放たれる際の煌めきは思わず息を呑むレベルです。
これでは「拡張が来たから遊ぶ」のではなく「この映像を味わうためにPCを整える」気持ちになってしまうわけです。
もう完全に趣味の範疇を越えて、自分への投資の一部になっていました。
温度や消費電力のチェックも欠かしません。
高負荷で長時間回しても70℃台後半で安定しており、空冷のしっかりしたクーラーを使えば十分対応可能でした。
以前の世代と比べると発熱コントロールの進化を強く感じます。
静音性について不安がありましたが、耳障りな轟音に達することはなく、長時間でも落ち着いてプレイできるのはありがたいことでした。
おかげで深夜のプレイも家族に気を遣わずに済みますし、その安心感は大きいです。
一方で、ストレージの課題は無視できませんでした。
最新拡張パッケージを追加したら想像以上に容量が膨れ上がり、1TBのSSDだと心もとなく感じたのです。
そこで私は2TBのNVMe Gen4に踏み切りました。
結果的にこの判断は正解でした。
毎回のパッチやアップデートがすぐに積み重なって容量を圧迫していく現実を考えると、余裕を持った構成こそ安心に直結するのだと思います。
ストレージが足りない、その一点で快適さが失われるのは避けたいですから。
思わぬ驚きもありました。
私は性能といえばfpsやベンチマークの数値だけで評価してしまいがちでしたが、実際に遊んでみて「フレーム生成」や「遅延低減」といった仕組みが体感に直結することを知りました。
DLSS4やReflex2の効果により、数値以上にレスポンスの軽さを肌で感じるのです。
この「自分の操作が即座に返ってくる心地よさ」という領域は、紙のスペックでは測りにくい部分です。
遊んでみないと絶対に理解できない。
だからこそ、プレイヤー自身の体験としての価値があるのだと強く気づかされました。
もちろん課題もゼロではありません。
4Kの最高設定でどんな状況でも完全に安定させたいのであれば、さらに上のGPUを選択する必要はあると感じました。
実際に大人数が集まるイベントのシーンでは、わずかですが底fpsの下降が見られたためです。
しかし、その落ち込みによってプレイ進行が大きく乱れるわけではなく、十分に受け入れられる範囲でしょう。
むしろ価格と性能のバランスを考えた場合、このクラスでここまでの表現ができること自体が驚きであり、大きな価値だと受け止めました。
最も大きな収穫は、このカードを導入したことでFF XIVという作品が本来持っていた力を存分に引き出せたことです。
これまで何度も見てきたはずの風景が、生まれ変わったかのように鮮やかな舞台に変貌していく。
ゲームであることを忘れて、旅をしているかのような感覚を覚えました。
「同じ世界なのに、こんなにも違うんだ」と心から思ったのです。
結局のところ、私が求めていたのは安定したプレイ環境と映像の説得力でした。
そして今回の構成は、その両方をきちんと満たしてくれたのです。
私は改めて実感しました。
PCパーツの進化は、単なる遊びの道具を超え、日常に感動を運んでくれるものなのだと。
これからFF XIVをより深く楽しみたいと思う人にとって、5070Tiは間違いなく一つの答えだと自信を持って言えます。
それが今の私の気持ちです。
Ryzen 7 9800X3D搭載PCの描画パフォーマンスを計測
人の多い都市に入っても平均100fps前後で動作し、24人の大規模レイドでも70fpsを切ることはほとんどなく、正直ここまでブレのない描画が出るとは思っていませんでした。
以前の環境ではレイドの途中で一瞬画面が引っかかることがあり、そのたびに「今のはやばかったな」と冷や汗をかいていましたが、それが完全に消え去った時の安心感は格別でした。
これなら仲間と集まる大切な週末の時間でも、パフォーマンスに気を取られずに思い切り遊べます。
実際に3D V-Cacheの恩恵を体感したとき、ちょっと感動しました。
単純なベンチの数値では分からない、微妙な引っかかりの解消。
ほんの一瞬のラグが消えただけで、プレイ体験はここまで変わるのかと驚きでした。
昔から自作PCを趣味としてきた私にとって、この変化の大きさは数字以上のものです。
思わずモニターの前で「これは買って良かったな」と声に出してしまったほどで、久々にPCパーツで心を躍らせました。
GPUにはGeForce RTX 5080を選びました。
正直、自分でも「ちょっと贅沢すぎやしないか?」と思っていましたが、今は胸を張って選んでよかったと言えます。
最近のFF XIVはキャラクター装備や街並みの描写が以前よりも細密になり、VRAMの消費はかなり増えています。
以前の環境で装備デザインが凝った人たちが集まると、微妙にフレームが落ちて「またか」と思うことがありましたが、この構成にしてからはそんなことを気にする必要すらなくなりました。
RTX 5070でも動くのは分かっています。
でも、大人数で集まる時に少しでも不安を抱えるのが嫌だった。
だからこそワンランク上を確保した選択が正解だと今は確信しています。
描画設定を少し落とすと140fps近く出て、その快適さには笑みがこぼれました。
高リフレッシュレートのモニターを繋げばさらにその差がはっきりと分かります。
それはまるで最新のスポーツカーを手にして、アクセルを少しだけ踏み込んだときの加速感のようでした。
普段は抑えて走り、しかし必要なときに一気に加速できる余裕。
気持ちの余裕にもつながっていますね。
冷却には空冷のハイエンドクーラーを採用しました。
正直、水冷を選ぶか最後まで悩んだのですが、今世代のCPUは発熱に配慮された設計がされていて、そこまで神経質になる必要はないと判断しました。
実際、長時間プレイしてもファンの音が気にならず、熱が部屋中にこもって不快になることもありません。
静かに遊べるって本当に大切なんです。
空冷で十分。
改めてそう思えました。
ストレージはPCIe Gen.4の2TB SSDを選びました。
これがまた快適でした。
アップデートのたびに肥大化するゲームサイズに対しても余裕があり、ロード時間が明確に短縮されています。
特に仕事の合間や帰宅後のわずかな時間に遊ぶ自分にとって、数十秒でも削れることがどれほどありがたいか分かるでしょう。
Gen.5も検討しましたが、熱対策がかなり面倒で、そこまでの利点は在りませんでした。
だからこそ今はGen.4がちょうど良いと思っています。
全体を通して言えば、この構成にして本当に良かったと感じています。
Ryzen 7 9800X3DとRTX 5080という組み合わせは「安定」と「描写の美しさ」を同時に掴めるもので、結果として後悔のない投資になりました。
もちろん費用を抑えるためにGPUのランクを下げる選択もできますが、このCPUをきちんと活かしたいのであれば、それに見合うGPUを組み合わせるべきなのです。
極上のプレイ体験。
まさにそんな表現がぴったりでした。
疲れて帰宅した夜でも、電源ボタンを押すと「よし、遊ぶか」という気持ちになれる。
そんな環境が整ったのは大きなことです。
40代になり若い頃のように夜通しゲームをする体力はないからこそ、短いプレイ時間をいかに快適に過ごすかは重要になります。
今の私にとってゲームは趣味であると同時に、自分の心を整える手段でもあります。
その大切な時間を安心して預けられるPC構成に出会えたことは、間違いなく大きなご褒美でした。
まさに宝物のような環境。
だから私は、この選択に一点の迷いもありません。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DY

| 【ZEFT Z55DY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58B

| 【ZEFT Z58B スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55IX

| 【ZEFT Z55IX スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55IM

| 【ZEFT Z55IM スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54H

| 【ZEFT Z54H スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
Core Ultra 7とRTX 5060Tiの組み合わせはお得かどうか
しかしいざ購入してみると、支払った金額を頭の中で思い返しながら「自分には少しオーバースペックだったかもしれないな」と感じてしまうものです。
私は家庭を持つ身なので、趣味に使えるお金にはどうしても制約があり、仕事や家計との兼ね合いを考えれば現実的な落としどころが必要になるんですよね。
私自身、実際にFF XIVを4K環境で試してみましたが、かつて旧世代のCPUで遊んでいた頃によく感じていた細かな引っ掛かりやフレームレートの波は、ほとんど姿を消していました。
数字を確認する必要すらなく、画面の中でキャラクターが滑らかに動くのを眺めながら「あ、これは快適だ」と素直に感じました。
そう思わせてくれる瞬間こそ、ゲームを遊んでいてもっとも大切な部分なのだと実感しました。
RTX 5060Tiについて言えば、過度な理想を抱かなければ十分な性能があります。
確かに「最高画質で4K、さらに120fps固定」というような夢を見てしまえば厳しいのですが、実際に画面を眺めながら操作すると、映像は十分に美しく、それでいて動作の止まりもなく快適です。
単純に遊んでいて疲れを感じない。
それだけで十分だと、私は強く思いました。
選手たちはまさに限界ぎりぎりで戦うような緊張感の中で動いていました。
しかし今回の自分の環境はそれとは違い、どこか余裕を持った描画力を備えており、その分プレイヤーであるこちらも焦りなく楽しめました。
余裕があるというのは、本当に心に落ち着きをもたらしてくれるんだと気づかされました。
今回の私の構成では特別な水冷システムを導入することなく、標準的な空冷クーラーと650Wクラスの電源のみで安定して稼働しました。
ケースだって市販のミドルタワーで十分です。
追加で大きなコストがかからなかったという事実が、とても大きな安心につながりました。
無理をして上位モデルのRTX 5070Tiも試してみましたが、性能が伸びる一方で価格面の重さがどうにも気になってしまい「これはちょっと現実的ではないかも」と感じてしまいました。
逆に5060Tiは、過剰なコストを求められず、必要十分な力を持ちながら最新のDLSSやニューラルシェーダにも対応しています。
これから数年先のアップデートや新作ソフトにもある程度備えられると考えると、むしろ堅実な選択でした。
長く安心して付き合える相棒。
私はスポーツ観戦が好きで、よく仕事に例えるのですが、どんなチームも一戦だけ活躍するスター選手よりも、毎試合安定して結果を出す選手を重宝しますよね。
極端なハイエンドを狙うのも夢がありますが、結局のところ「安心して任せられる選手」に投資する方が満足度は長く続く。
その方が健全だと心から思います。
もちろん「最高画質を余すことなく楽しみたい」という気持ちを持っている人も少なくないはずですし、それを否定するつもりはありません。
そういう意味でこの組み合わせは、日常生活と両立できる最適解だと自信を持って言えます。
結果的に私は「買ってよかった」と感じました。
価格と性能の折り合いを見事につけ、安定したプレイ環境を長く楽しめる。
その満足感がとても大きいのです。
便利さや数字には表れない余裕や落ち着きがあるからこそ、選択が正しかったと思えるのだと思います。
これまでいくつものPCを組んできましたが、結局のところ自分が日々求めていたのはこの落ち着きだったのかもしれません。
無理なく手が届き、自分のライフスタイルに馴染む構成を選ぶということ。
それが中長期での満足度につながるのだと、今回改めて確信しました。
心地よさ。
長時間プレイでも安定動作させる冷却&温度管理の考え方
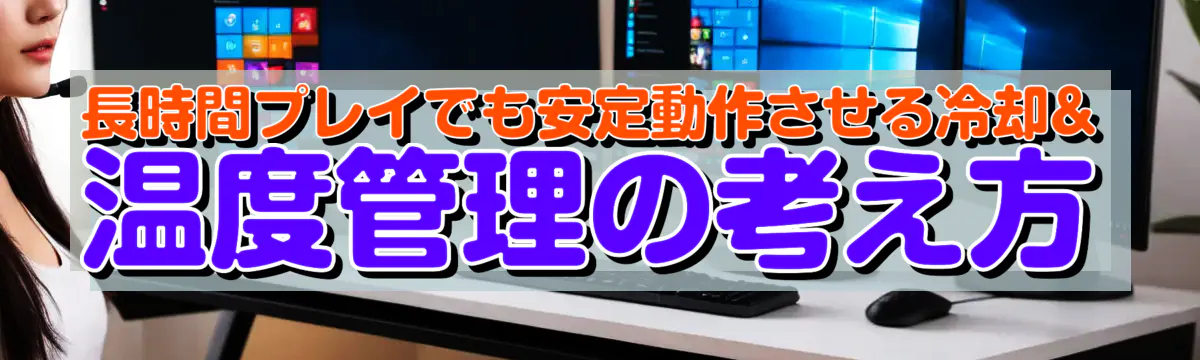
空冷と簡易水冷、それぞれのメリットと選び分け
空冷か水冷か、どちらがいいのか。
これはシンプルなようで実は深いテーマです。
私自身、これまでに何度も自作やBTOモデルで両方を試してきました。
その中で感じたのは、性能を最大限に引き出したい場面では水冷、気兼ねなく長く付き合いたいなら空冷、という判断がもっとも納得できるということでした。
要するに「目的が何か」で答えが変わる。
それがこの選択の本質だと思っています。
空冷には昔から独特の安心感があるんです。
ごついヒートシンクとファン、それだけで成立する仕組みのわかりやすさがいい。
私はCore Ultraの世代で空冷を組んだ時、正直そこまで温度が上がらなかったのに驚いたんです。
冷却性能は十分。
しかも掃除も楽ですし、万が一の交換も数本のネジを外せば終わる。
シンプルさ、それこそ空冷の武器です。
ただし空冷でも厳しい場面があります。
高性能GPUを積んで長時間プレイをしていると、どうしてもケース内の空気が熱を帯びます。
結果的に効率は落ちていきます。
夏場は特に厳しく、汗をかきながら「これは限界か…」なんて呟いた経験も一度や二度ではありません。
そういう苦い記憶を救ってくれたのが簡易水冷でした。
冷却水が熱を拾い、ラジエーター越しにケース外へ逃していく仕組み。
シンプルながら冷却の余裕は段違いです。
私が夏に試した際には、CPU温度が以前より10度も下がりました。
高負荷のレイドバトルでもフレーム落ちがなく、ゲームが滑らかに続いてくれるあの安心感は言葉にしがたい体験でしたよ。
もちろん水冷は夢の装置ではありません。
ポンプの寿命、冷却液の劣化、設置スペースの制約。
課題はいくつもあります。
特に360mmラジエーターを載せようとすれば、ケース選びから真剣に考えなければならない。
思い出すのは、大人数でのダンジョン挑戦の際のこと。
空冷の時にはCPU温度がじりじり上がり、フレームがほんの少し落ちる瞬間がありました。
ゲームの展開が熱いときにわずかに揺れる画面。
小さなことですが、没入感を冷や水で流されるような気持ちになるんです。
それが水冷に変えてからはなくなった。
グラフィックの滑らかさが守られることで、心から安心して楽しむことができました。
ゲームと自分が一体になれた感覚。
あれは本当に大きな違いでしたね。
私は今では、空冷と水冷を「日常と挑戦」で区別しています。
普段使い、たとえば家族がブラウジングや動画を見るような環境なら、大型空冷クーラーを迷わず選びます。
誰が触っても安心して勧められる。
けれど、本気のゲーム環境を新しく組むなら水冷を選びます。
真夏でも耐えて、夜でも静か。
メンテナンスの煩わしさが頭をよぎっても、それと引き換えに得られる快適さを考えると迷いはありません。
重要なのは、自分がどんなシーンでそのPCを使うかを冷静に想像することだと思います。
作業か、ゲームか。
短時間か、長時間か。
趣味としての満足度を優先するのか、それとも日々の安心運用を優先するのか。
この問いに自分なりの答えを出すことが一番大切です。
冷却方式の選択は単なる性能比較ではなく、「これから数年間どんな体験をしたいか」を決める選択なんです。
だから私は人に相談された時、まず「あなたにとって譲れないポイントは何か」と聞きます。
それが空冷か水冷かを決める一番の指針になるからです。
思えば、冷却の話は少し堅苦しく聞こえるかもしれませんが、結局は快適に楽しく使うための準備に過ぎないんですよね。
CPU温度やファンの音に振り回されず、目の前の冒険や作業に集中する。
その時間が、最高に贅沢な時間だと思うんです。
だから私は、自分自身で選んだ方法を誇りにしたい。
そして、心地よい没入感。
静音性を重視する人向けの空冷クーラー選びのコツ
気づかぬうちに時間を忘れ、画面に没頭している自分にふと気づく瞬間、耳に残るのはケースの奥で回っている冷却ファンの音です。
静まり返った夜にカリカリとした回転音が響くと、一気に現実に引き戻されてしまう。
せっかくの没入感が壊れてしまうのは残念で、だから私は「どんなに冷えるか」よりも「どれだけ静かか」を優先してクーラーを選びたいと思うようになったのです。
安心して集中できるために必要なのは、性能の数字以上に静音性だと実感しています。
昔はCPUの発熱がひどく、水冷じゃないと安定運用できないなんて言われていた時代もありました。
しかし今は状況がまるで違います。
技術が進み、省電力と発熱抑制が並行して進化したおかげで、空冷であっても適切なエアフローさえ確保できれば問題なく動かせる。
その事実を知ってから、私は空冷クーラーの存在を見直すようになりました。
特に印象的だったのは、初めて二塔構造のモデルを試したときでした。
見た瞬間は正直これ、本当に収まるのか?と驚きましたね。
ところが実際に取り付けてみたら、ケース内部の空気が秩序立って流れていき、CPU温度が安定することに驚かされました。
職場でヘトヘトになって帰宅し、やっと落ち着ける時間にあの静けさがあるのは、想像以上に心を支えてくれるものです。
安心感ってこういうことだと思いました。
静かさを求めるなら、冷却の仕組みそのものよりもファンの作りに注目するべきです。
流体軸受や磁気ベアリングを採用したファンは寿命が長くて、あの耳障りな回転音を出しにくい。
さらに羽根の形状に工夫があるモデルでは低速でもしっかり風が流れ、ヒートシンクを冷やしてくれます。
だからファンの質が違うだけで、働きながら横で本を読む家族の空気まで壊さずに済むんです。
些細なことですが、その静けさがあるかどうかで生活の質が変わる。
小さなことの積み重ねが、結局は大きな心地よさにつながると実感しています。
ただ注意が必要なのはサイズです。
私は過去に巨大な空冷クーラーを勢いで買ったものの、メモリと干渉して取り付けられず、結局泣く泣く手放した経験があります。
そのときの脱力感といったら…。
机の上に広がった部品を見て深いため息をついたあの光景は、今でも忘れません。
それ以来、必ずケースの寸法やメモリの高さを確認するようにしています。
ひと手間だけれど、ここをサボると本当に痛い目を見る。
私は今も強くそう思いますね。
最近ではネットのやり取りを見ても「水冷はちょっと大げさだった」という声が多くなっています。
以前はハイエンドPCと言えば水冷がひとつの象徴だったのに、いまや静音と安定の両立を重視して空冷に戻る人が少なくない。
この流れに私も共感しています。
無駄な装飾ではなく、日常でちゃんと役に立つものに価値を見出す。
私はこの風潮を肯定的に受け止めています。
もちろん、ファン制御がきちんとできているかどうかが快適さの分かれ目になります。
BIOSや専用ソフトでファンカーブを調整すれば、環境がぐっと落ち着きます。
FF XIVのように突然負荷が跳ね上がるタイトルではこの差ははっきり現れます。
温度が上昇しても急激に騒音に変わることがなく、すっと落ち着いたまま運用できる。
このストレスのなさが本当に大事なんです。
私は実際にNoctuaのファンを導入したとき、その静かさに心底驚かされました。
PC自体が息を潜めたような感覚とでも言えばいいでしょうか。
思わず「え、こんなに違うものか」と声に出したくらいです。
それ以来、静けさを優先するなら空冷、と決めています。
その後に試したDEEPCOOLやサイズのモデルも進化が感じられ、音質がやわらかく、不快な高音がほとんど消えていました。
結局どう選ぶのがいいか。
私は、大型の空冷クーラーをうまく取り入れつつ、ケース全体のエアフローを意識してファンを細かく調整するのが一番だと考えています。
実際に4K画質で重量級のタイトルを動かしていても、きちんとした構成なら問題なく安定しています。
極端な温度まで上がらない限り、不要な心配はいらない。
空冷こそ安定性と静音を兼ね備えた最適解だと、確信しているのです。
静けさは贅沢な要素ではなく、日々の生活に寄り添う大切な基盤です。
だから私は、夜にPCの前で時間を忘れて没頭できる瞬間がとても愛おしい。
誰にも邪魔されず、ただしんとした環境に身を置いて、自分の時間を過ごせるのです。
やすらぎ。
仕事を頑張った日の夜に、安心して好きなことを続けられる環境が整うことほどありがたいものはありません。
4Kプレイ時に重要になるケース内エアフロー改善策
4K環境でゲームを楽しむなら、まず真っ先に考えるべきは冷却対策だと私は思います。
どれだけ最新のCPUやGPUを組み合わせても、ケース内の空気が滞って温度が上がれば性能はあっさりと頭打ちになります。
私は何度も痛感してきましたが、安定したゲーム体験は派手なパーツ性能よりも、基盤になるエアフロー設計の良し悪しに左右されるのです。
正直、これは誰よりも自分自身に言い聞かせたいことでもあります。
過去に私は、見た目重視でガラスフロントのケースを使っていました。
最初は光り方に満足していたのですが、長時間プレイをするとGPUの温度がみるみる上がり、フレームレートが荒れる場面が頻発したのです。
そのたびに「あれ、なんでこんなに不安定なんだ」と苛立ちました。
せっかく投資したのに性能を引き出せないむなしさは正直きつかったです。
その後、思い切って前面メッシュタイプのケースに切り替えたところ、温度が平均で7度近くも下がり、録画や配信と同時にプレイしても安定するようになった瞬間、「ああ、自分は今まで大きな勘違いをしていた」と心底思いました。
冷却の基本は実にシンプルで、吸気と排気のバランスです。
だからこそ私はフロントに14cmファンを2基以上配置し、背面に1基、トップにも2基置いてバランスを取る工夫をしました。
そのちょっとした手間で安定感がぐっと増すのです。
正直、派手な見た目のケースに惹かれる気持ちはわかります。
ですが、吸気口が狭いケースだと、まるで流れの止まった川のように熱が淀む。
機能性を軽視してはいけません。
特に驚かされたのはSSDの発熱でした。
録画しながら4Kプレイをしていると、NVMe Gen.5 SSDが手で触れないほど熱くなり、ケース全体の温度にまで影響が出ました。
BTOモデルを試したとき、小型ファン付きのヒートシンクが取り付けられていたのを見て感心したものです。
細かい工夫があるかないかで、プレイ中の不安感はまったく違う。
私はそのとき心から納得しました。
やっぱり備えは表に見えない場所ほど大切なんですよね。
ファンの回転数についても管理が欠かせません。
常に全力で回してしまえば冷却できるかもしれませんが、今度はノイズが耳障りになり、夜遅くのプレイでは集中を削がれます。
結果として温度の上昇を安定させつつ、耳障りな騒音も抑えることができたのです。
小さな工夫の積み重ねが快適さにつながるのだと、しみじみ実感しました。
水冷クーラーについても勘違いは禁物です。
一見すると大型ラジエーターを付ければすべて解決するように思えますよね。
私も以前360mmラジエーターをフロントに装着したのですが、CPUは冷えても排熱の熱風がGPUに直撃して逆にGPUの温度が跳ね上がるという失敗をしました。
ファンは常に全開で、さすがに頭を抱えました。
最終的にトップマウントに変更して、フロントをメッシュ吸気にしたことで環境は落ち着きましたが、そのときは「本当に設計を甘く見ると痛い目に遭うな」とつぶやいたのを今でも覚えています。
人はやっぱり、スペックの数字に惹かれるものです。
ですがそれだけに振り回されて冷却を軽んじるのは本当に危険だと私は思います。
高性能のGPUを刺しても、温度対策が不十分なら結局使いこなせない。
つまり数字に投資したつもりが、冷却不足で性能を半分しか発揮できない。
そんな事態は本当に悔やまれるばかりです。
4Kで本気で遊びたいなら、まずケースとエアフロー設計にこだわること。
高エアフロー対応のケースを選び、吸気と排気の整理を怠らず、熱が籠らないよう丁寧に組む。
これが最も確実な答えだと思います。
ハードな裏技ではなく、当たり前のシンプルな工夫こそが実力を引き出すのです。
熱こそ最大の敵。
それを抑えられれば、パーツはようやく本来の性能を見せてくれる。
ゲームの映像もまるで別世界のように滑らかさを増します。
私は何度も失敗と調整を繰り返してきましたが、結局のところ、派手な見栄えよりも堅実さが大切だと学びました。
時間もお金もかけたのに期待通りに動かないときの後悔は本当にしんどいものです。
同じ思いは誰にもしてほしくない。
だからあえて声を大にして言いたい。
もうこれに尽きます。
映像体験を高めるFF XIV向け周辺機器の選び方
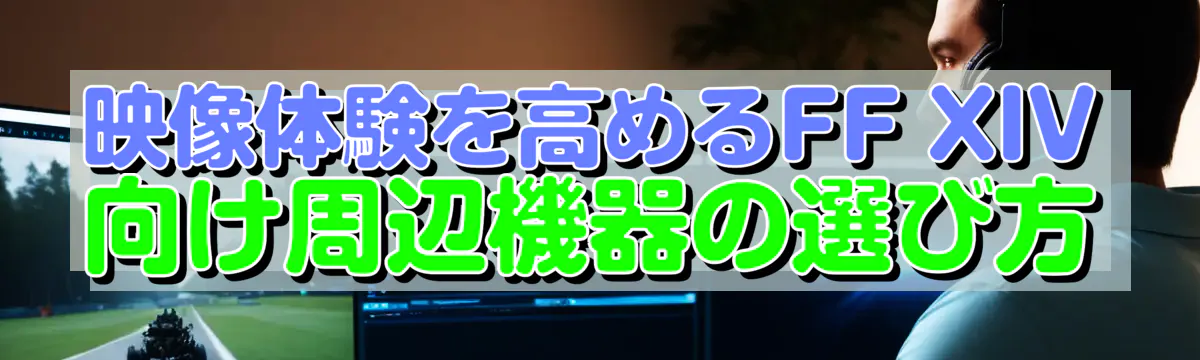
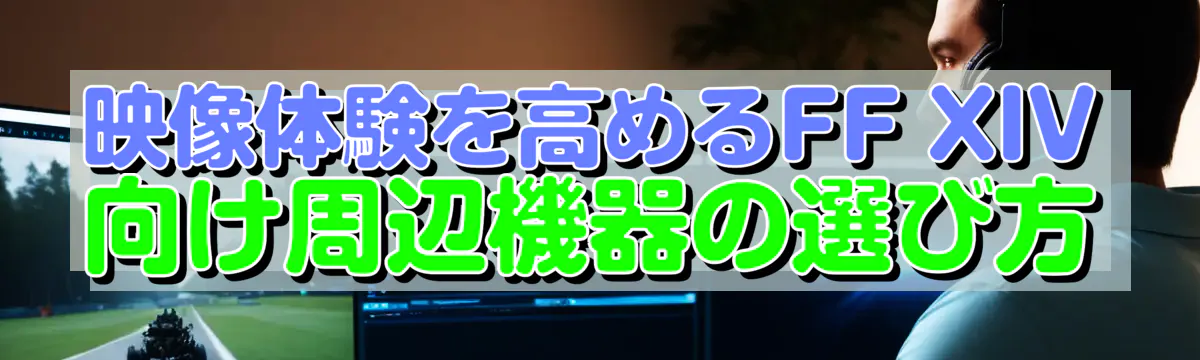
4Kモニターを購入する前に確認しておきたいチェックポイント
4Kモニターを選ぶにあたって私が強く言いたいのは、見た目の美しさだけに気を取られてしまうと痛い目にあうということです。
解像度が上がればその分だけGPUへの負担も跳ね上がります。
私は以前、それを実感しました。
軽い気持ちで「4Kなら最高でしょ」と買い替えたのですが、手持ちのGPUが古く、いざ使ってみると映像はカクつき、ファンは休みなく唸り続け、正直ものすごくストレスでした。
性能の見積もりを誤ると、投資が無駄になるんですよ。
痛感しましたね。
ただ、ハードのスペックが高ければ安心、という話でもないんです。
規格の対応状況も大事です。
DisplayPortやHDMIの最新規格に非対応だと、GPUがどんなに優秀でもモニター側が受け止めきれず、リフレッシュレートが制限されるんです。
私はそこを見落としてしまい、購入直後に「ちょっと待て、なんか違うぞ」と頭を抱えた経験があります。
その時のがっかり感、忘れられません。
買う前はテンションが上がっていたのに、数日でその熱が見事に冷めました。
サイズ選びも本当に侮れません。
一方32インチ以上になると迫力は抜群ですが、机の奥行きが足りないと首や肩に負担が出る。
自身のワークスペースと生活リズムを踏まえて考えないと、見た目の派手さに振り回されます。
快適さこそが本質です。
リフレッシュレートの違いも見逃せません。
昔は60Hzで別に困らないと思っていたんです。
ところが、思い切って144Hz対応に買い替えてみると別世界でした。
キャラクターが自然に動き、操作の反応まで心なしか速くなった感覚があったんです。
最初は「本当にそこまで違うのかな」と半信半疑でしたが、いざ体験してしまうともう後戻りできません。
映像の滑らかさは、遊び方や感じ方そのものを変えてしまう。
そう言っても大げさではないですね。
パネル方式も要チェックです。
私は仕事でも映像編集をよくするので、IPS一択ですが「もうここまで来たか」と技術の進化に素直に驚いています。
HDRも見逃せないです。
光の演出を楽しむようなゲームでは、HDR対応か否かで臨場感が全然違うんです。
ただし、「HDR対応」と表示されていても実際は輝度不足で見劣りする製品が多いのも事実。
私はかつて安価なHDR対応モニターを買ったのですが「これって本当にHDR?」と疑うような表示でがっかりしました。
安さに負けた自分を責めましたよ。
最低でもDisplayHDR600クラスを狙うべきだと、経験から断言できます。
価格差以上の違いが出るからです。
それから、接続端子の数は軽視しがちですが、実利用では意外なほど差が出ます。
私はゲーム用PCのほかに仕事用ノートもつなぎ、さらに映像機器も接続するので、端子が少ないと毎回ケーブルを抜き差ししなくてはいけません。
これが積み重なると、予想以上にストレスです。
数の多さや配置の工夫が、日々の使い勝手を大きく左右する。
その価値を身をもって知りました。
スピーカーについても触れておきたいです。
確かにモニター内蔵のものは物足りなさが残ります。
ただ、ちょっと動画を見る程度なら十分ですし、ヘッドセットをしたくない時にぱっと使える便利さは侮れません。
高音質ではないけれど、あるとないとでは使い心地が違う。
私は何度も「ついていてよかった」と感じてきました。
保証とサポート。
ここが最後の決め手になることもあります。
モニターは数年単位で使用する高価な道具です。
長く使うからこそ安心感を買うことが大切なんです。
その安心が次の踏み出しにもつながっていきます。
だからこそ断言します。
この条件を満たした一台を手にしたとき、初めて「これは良い買い物だった」と言えるのだと思います。
私自身の失敗と成功を経てたどり着いた答えです。
その瞬間の納得感。
そして後悔のなさ。
これが本当に重要なんです。
自分にとってストレスのない一台を選ぶ。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R61BQ


| 【ZEFT R61BQ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63E


| 【ZEFT R63E スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59B


| 【ZEFT Z59B スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FD


| 【ZEFT R60FD スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55CP


| 【ZEFT Z55CP スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
操作感を変えるゲーミングキーボードの選び方
FF XIVを存分に楽しむのに本当に必要なのは、映像の美しさやフレームレートのなめらかさではなく、実際には手元で操作するデバイスだと私は思っています。
最初はパソコンの性能ばかり気にしていたのですが、結局のところ、操作の精度や反応速度の差がプレイ体験を大きく左右するのです。
だから、キーボード選びを疎かにすると、いくら映像が美しくても途中でストレスが積み重なり、楽しさどころか苛立ちが増えるばかりになります。
この三つさえ押さえておけば、長時間プレイしても大きな後悔はないと思っています。
特に気を使うのがキー軸の違いです。
リニア軸の軽い感触は指が疲れにくく、タクタイル軸は誤操作を減らしてくれる安心感がある。
そしてカチッとしたクリック感が好きならクリッキー軸がやはり魅力です。
以前、深夜のボス戦で押したつもりのスキルが出ず、全滅の原因になった時には、文字通り頭を抱えました。
あとで振り返れば、「たったこれだけの違い」と笑えるのですが、その時は笑えたものではない。
小さな差が大きな結果を生むのだと、身をもって思い知らされました。
たかが軸、されど軸というわけです。
入力の正確性もまた無視できません。
FF XIVは多人数で連携する大規模戦闘が売りのひとつで、リミットブレイクのタイミングが揃わなければ一気に劣勢になります。
私は過去に安物のオフィス用キーボードを使っていた時期がありました。
同時入力に不具合が出て、スキル発動を仲間と合わせられず、明確に敗北を招いた経験があります。
その時の「自分さえきちんと操作できていれば」という悔しさは、本当に後を引きました。
結局、安物買いの銭失いだったと後悔するしかありませんでしたね。
派手に見えるライティング機能も意外に役立ちます。
夜に部屋を暗めにして遊ぶと、特定のキーが光っていてすぐ分かるのは思いのほか助かるのです。
私は回復職を担当することが多いのですが、緊急時には一瞬で操作しなければならない場面が数え切れないほどあります。
だから、色分けしたキーを見て即反応できたとき、仲間を救えた安堵感は何物にも代えられません。
守れた喜び。
この一言に尽きます。
もちろん、耐久性へのこだわりも大切です。
特に私のように平日の夜や休日は長時間ゲームに没頭してしまう人間にとって、数か月で壊れるような製品はただのストレスです。
過去にはチャタリングに悩まされたこともあり、意図せずスキルが暴発するあの瞬間の気まずさと不快感は、二度と経験したくありません。
多少高くても、しっかりした作りのものを買った方が、長い目で見ればむしろ出費を抑えられる。
精神的な安心も得られる。
音の問題も見逃せません。
私は夜中にプレイすることが多く、寝室にいる家族にキーボードの音が響いてしまうことがありました。
あの「カチャカチャ」という音は、自分にとってはゲームのリズムでも、家族にとってはただの雑音にしか聞こえないのです。
最近は静音軸のモデルを愛用していますが、正直ここまで気を使わずに没頭できるのかと驚きました。
大切なんです、これは本当に。
さらにサイズ感です。
昔はフルサイズのキーボードを当然のように使っていました。
ただ、長時間のプレイで肩が異常に重くなることがありました。
そこで思い切ってテンキーレスに買い替えてみたら、これが正解でした。
腕の動きが減った分、肩への負担も軽くなり、ゲーム後の疲労感まで減ったのは正直驚きでした。
小さな改善が、大きな快適さを生むと実感しました。
市場の変化も面白く感じています。
最近はゲーム専用メーカーだけでなく、オフィス機器で有名なメーカーまでが続々とゲーミング分野に参入する流れがあります。
去年、とある透明筐体のモデルを試したとき、見た目があまりに独特で「おっ、面白いな」と声が出てしまいました。
でも実際に使ってみると、外見の軽さに反して驚くほど頑丈な打ち心地があり、そのギャップに驚かされましたね。
この数年での品質の底上げは、本当に想像以上でした。
結局どう選ぶべきかを整理すると、私はこう考えています。
FF XIVを最高の環境で楽しみたいなら、前提としてメカニカル方式を選び、その上で耐久性と入力精度を第一に重視すること。
そして生活環境やプレイスタイルに合わせて、静音性やライティング機能、サイズ感を吟味していく。
これが最も後悔のない選択です。
ゲーム体験を支えるのは、映像の鮮明さだけではなく、手元の操作感だという事実。
だからこそ、私は今も妥協せずにキーボードを選び続けています。
それがゲームを「楽しさ」だけでなく「心地よさ」に変える、一番大切な要素だと信じているからです。
腰への負担を減らすゲーミングチェア選びの実体験
少し値が張っても、信頼できるメーカーの調整機能が整ったゲーミングチェアを選ぶことが最終的に一番の正解なのだと。
安さに惹かれて何度も中途半端なチェアを買い替え、その都度腰痛に悩まされてきた失敗の積み重ねがあったからこそ、体験を通じて自分なりの答えにたどり着いたのだと思います。
パソコンやグラフィックボードに大金を投じても、腰が痛くて座っていられなければ全部が無駄になる。
このことは痛烈に身に沁みました。
昔を振り返ると、安価なオフィスチェアに座り続けてFF XIVを何時間も遊んでいたことがあります。
そのときは夢中でプレイしていたのですが、翌日の朝会で椅子から立ち上がる瞬間に「うっ」と声が出るほど腰が張ってしまい、仕事への集中どころではありませんでした。
腰をかばいながらのゲームは全然楽しくなかったし、そのストレスがそのまま翌日のパフォーマンスにも影響しました。
趣味が足を引っ張り、仕事の成果までも落としてしまう危うさを実感した瞬間でした。
思い切ってゲーミングチェアを購入したのは、そんな後悔を繰り返したくなかったからです。
最初に座ったときの安定感は今でも忘れられません。
背中を支えるランバーサポートを自分の腰の位置にきっちり合わせると、それまで意識しても保てなかった姿勢が自然と整い、体がスッと軽くなるように感じました。
まさに「ああ、やっと出会えた」という感覚でした。
以前の椅子のように座面が沈み込んで体が歪んでいくこともなく、包み込まれるような安心感に心から驚きました。
さらに驚いたのは、プレイ中の集中力が明らかに途切れにくくなったことです。
長時間の高解像度プレイでも、腰に痛みが出ないだけで冷静な判断力が保てる。
これはゲームに限らず、在宅ワークでの会議や資料作成でも同じ効果を感じています。
かつては腰を庇うあまり打ち合わせ中に姿勢を崩し、相手にだらしない印象を与えてしまうこともありましたが、今は違います。
椅子一つでここまで変わるとは、本当に思いもしませんでした。
以前の椅子はリクライニングが硬く、角度を変えるたびに「ギギギ」と不快な音を立てました。
気分転換どころか余計に疲れを感じるだけ。
対して今のチェアは、ワンタッチでスムーズに動きます。
小休止のタイミングで背もたれを倒し、深呼吸をし、また前を向く。
ストレスのない動作が自然と自分のリズムを整えてくれています。
これは小さなことのようでとてつもなく大きいんですよ。
キーボードとマウスを繰り返し操作する作業では、腕の位置がしっかり合わないと肩が固まり、最終的に腰にまで痛みが響きます。
体全体がスムーズに動く感覚は本当にありがたいものです。
支えがひとつ増えるだけで、こんなにも楽になるとは正直驚きでした。
もちろん、過去の選択には悔しい思い出も残っています。
数年前、安さに負けて無名のブランド椅子を購入したことがありました。
しかしほんの数週間でクッションはへたり、背もたれは心もとなく、結果は腰痛の悪化。
さらに買い直し費用まで発生してしまい、まさに「二度手間で余計な出費」でした。
あのときの苛立ちはまだ忘れられません。
本当に痛感しましたよ。
新しい椅子に腰を下ろしたときの感覚を覚えています。
張りのある座面に体を預けた瞬間、「これは違う」と心の中で思いましたね。
数時間遊んでも腰の重だるさがなく、立ち上がるときも自然にスッと動ける。
以前なら「よいしょ」と顔をしかめながら立ち上がっていたのに、その必要が消えてしまった。
たった一脚でここまで生活が変わるなんて、当時は想像できなかったことです。
その衝撃と感動は、今も鮮明に残っています。
在宅ワークが増え、一日中パソコンの前にいるようになってからも、この椅子は私を助け続けてくれました。
腰痛が驚くほど減り、仕事の能率も確実に伸びた。
余計な疲労を翌日に持ち越さず、集中してタスクを進められる安心感。
これは数字で測れない価値です。
健康と成果を両立させるための基盤が、この椅子によって整ったと実感しています。
腰を守ること。
それがすべての土台。
そして集中力を持続させること。
この二つを叶えてくれる存在が、快適な椅子なのです。
多くの人はPCのスペックに意識を向けますが、実際の生産性や楽しさを大きく左右するのは、座り続けて過ごす時間の質だと私は確信しています。
だからこそ、長時間FF XIVをプレイするにしても長い会議に臨むにしても、腰の不安がないだけで成果はまるで変わるのです。
私は今、自信を持って言えます。
パソコンに数十万円を投資するなら、数万円の椅子には迷わずお金をかけるべきだと。
椅子は単なる家具ではなく、健康と趣味と仕事をつなぐ大切なパートナーです。
信頼できるメーカーから選ぶことが正解であり、腰を守るという選択が最高の体験とパフォーマンスを生む第一歩になるのだと、心から確信しています。
FF XIV用ゲーミングPC選びに関するよくある疑問
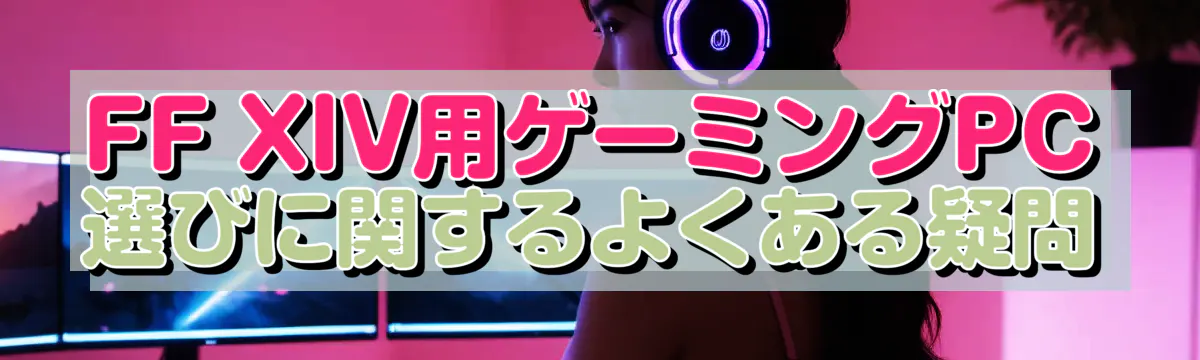
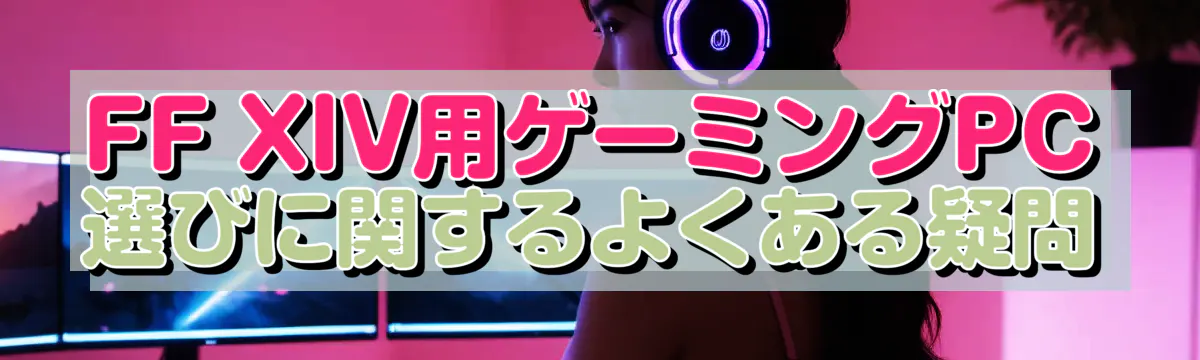
FF XIVを4Kで動かすのに最低限必要なGPUはどれ?
FF XIVを4Kで本当に快適にプレイしようと思ったら、避けて通れないのはグラフィックボードの性能です。
フルHDやWQHDではそれなりに優秀だったカードが、4Kになると急にフレームレートが不安定になり、人が集まるシーンでは一瞬でカクつき出す。
あの瞬間は正直、がっかりしましたね。
ここまで環境差が出るのかと痛感したものです。
私の経験上、RTX 5070やRadeon RX 9060XTといった中堅どころのカードも設定を控えめにすれば「動く」ことは動きます。
ただ、最高品質まで引き上げると、バトルシーンや街中で処理がついてこなくなる。
拡張直後の人がごった返す状況だと、ただ突っ立っているだけで画面が揺れるような感覚になるんです。
そのとき心の中で「結局GPUの差ってこういう形で出るんだよな」とつぶやいていました。
苛立ち半分、納得半分でした。
そこから思い知らされたのがVRAMの容量の大切さです。
6GBや8GBだと場面転換で引っかかりが多く、ムービーの読み込みでも落ち着きがなくなる。
一方で16GB積んだカードに換装したとき、あまりにスムーズになって驚きました。
やはり余裕があるって大事なんだなとその瞬間に気づいたんです。
安心しましたよ、心底。
実用的に見ると、現行世代ならRTX 5080やRadeon RX 9070XTあたりが「最低ライン」と言えます。
どちらも余裕のVRAMと高速メモリを備えており、長時間の4Kプレイにもしっかり応えてくれる。
私も実際にこのクラスに換えたとき、もうWQHD環境に戻ることはできなくなりました。
細部まで緻密に描かれる質感や空気感が鮮やか過ぎて、ただゲーム内を歩いているだけで嬉しくなってしまった。
これはちょっとした感動でした。
一度そのクオリティを体験してしまうと、以前の環境に戻るのは本当に辛いものです。
普段は気にならなかった通勤電車も、一度グリーン車の静けさを味わったらもう普通車が窮屈に感じる、そんな感覚に似ています。
滑らかで美しい世界が当たり前になると、人間は元には戻りづらいんです。
GPU選びは本当に生活の快適さを左右するほどの要素なんだと実感しました。
私が重視しているのはパフォーマンスだけではありません。
昔のハイエンドGPUは力はあるけれど騒音や発熱がひどく、プレイ中にファンの音ばかり気になっていたことがあります。
正直「ゲームを楽しむどころじゃない」と感じる場面も多かった。
しかし最新世代では効率が大幅に改善され、静かで快適にゲームへ没頭できる。
これは年を重ねてから特にありがたく感じる進化です。
FSR 4によるアップスケーリングやフレーム生成機能はかなり優秀で、工夫すれば4Kでも軽やかに遊べる。
「本当にこの価格でここまでできるのか」と思わず声に出したくらいです。
コストを抑えたい人には強い味方になりますね。
もちろんGPU以外も全体設計に欠かせません。
CPUであればCore Ultra 7 265KやRyzen 7 9800X3Dといったクラスが欲しいところですし、メモリは最低でも32GBにしておいた方が安心です。
ストレージも大容量のNVMe Gen4を備えていないと、パッチ更新のたびに容量不足で頭を抱えるはめになります。
私も過去にそれで毎回いらないデータの整理に時間を費やしました。
これ、なかなか面倒なのです。
さらにケース内の冷却も軽視できません。
いくら高性能のGPUを入れても、熱だまりがある環境では本来の性能を出せません。
私の場合、GPUを替えるよりよほど効果を感じたこともありました。
ほんの少しの工夫が、大きな差につながるんです。
最終的に私が出した答えは、RTX 5080やRadeon RX 9070XTクラス以上を中核にした構成が最も現実的で後悔がない、というものです。
これより下のクラスは動くには動きますが、FF XIVの世界を「心から楽しむ」にはどうしても不足を感じました。
過去に私は価格を優先して下位のGPUを選んだことがありますが、結局すぐ限界が来て買い替える羽目になり、トータルでは余計に費用がかかってしまいました。
40代になって時間も限られる中で、快適な環境を整えて一瞬一瞬を楽しむ。
その方がコスト以上に得られるものが大きいと、私は身をもって実感しています。
FF XIVを4Kで本気で楽しむなら、遠回りせず上位クラスを選ぶこと。
それが一番の近道です。
CPUはインテルとAMD、結局どちらを選ぶのが安心?
私の率直な結論を先に言うと、配信や同時作業も含めた安定性を重視するならインテル、映像美に徹底的にこだわりたいならAMD、とりわけX3D搭載モデルを選ぶのが良いと思います。
そしてその迷いの過程こそ、多くの方が直面する悩みと同じだと思うのです。
私がインテルに強い信頼を置いている理由は、とにかく安定した動作です。
大規模レイドやプレイヤーが集まる都市部など、フレームレートが落ち込みやすいシーンでも、動作が底割れすることが少ないのです。
ゲーム中に画面が一瞬でも止まったりカクついたりすると、それだけで一気に気分が削がれます。
そうしたストレスが極端に少ないのは、本当にありがたいことだと感じました。
長時間のプレイを繰り返していくうえで、安心して身を預けられる存在。
安心感。
これは数字上の性能比較だけでは見えない価値なんです。
逆にAMDのX3Dモデルは、初めて触ったときに「おお、これはすごいな」と思わせてくれる瞬間があります。
キャッシュ構造のおかげで特定の場面で驚くほどスムーズに描画され、映像がより生き生きと見えるのです。
特に光やエフェクトが重なるシーンでは、その強みがはっきりと現れます。
画面の中に吸い込まれ、気づいたら現実の存在を忘れてしまうような没入感。
それを味わえるのはAMD側の魅力だと断言します。
私は実際にCore Ultra 7とRyzen 7 X3Dを並行して使ってきました。
仕事の合間にブラウザを立ち上げ、資料を見ながらオンライン会議に参加しつつ、その裏で動画を再生している。
こうした同時処理の多い使い方だと、やはりインテルに分があります。
全体がスムーズで、途中で動作が引っかかるようなこともなく、心が乱されない。
一方で、いざ深夜に腰を据えてFF XIVを堪能する時間になると、AMDでの体験が忘れられないのもまた事実です。
とはいえ、選択はシンプルです。
作業もゲームも両立させたいのか、それともただ純粋に映像体験に浸りたいのか。
その軸を決めれば迷いは消えます。
だから私は声を大にして言いたい。
「自分が求める体験に素直になればいい」と。
選び方は人それぞれで、どちらが正解というわけではないんです。
実際、最近のCPUはAI処理やNPU機能といった新しい機能にも力を入れていますが、少なくとも現時点でFF XIVに直接関係することはありません。
ただ未来を考えると話は変わってきます。
動画制作や配信の効率化に関わるとき、この機能は絶対に効いてくる。
3年先を考えるなら、CPUを「ただのゲーム用」として見るか「ライフスタイルを支える基盤」として見るかで選択の重みが変わります。
これは悩み甲斐のある切り口だと思いますね。
忘れてはいけないのは、CPUだけでは快適環境は完成しないということ。
GPUやメモリとの組み合わせも非常に重要です。
FF XIVのようにグラフィックの負荷が大きいゲームではGPUが主役のように見えますが、実際にはCPUが最低限の滑らかさを下支えすることで快適さが成立する。
つまり、片方だけ最新世代にしても本当の意味での快適には届きません。
だから私は迷っている人に必ず伝えます。
旧世代では必ず不満が出ますし、どちらを選ぶにしても新しいものを選ぶことが最初の条件になるのです。
正直なところ、私も購入前には相当悩みました。
スペック表を見比べて、何が違うのかに頭を悩ませ、レビューを追いかけて、結局どちらを選べばいいのか分からなくなってしまう。
最終的に決め手となったのは、実際のプレイにおける体感の差です。
週末に仲間と24人レイドに挑んだとき、途切れることなくスムーズに続いたインテルの動作は、まるで「背中を支えられている」ように感じました。
これには抗えない安心感がありましたよ。
でも、AMDを選んだ人たちが「やっぱりこれにして良かった」と語る言葉を聞けば、その気持ちも分かります。
没入感を愛するゲーマーにとって、AMDは間違いなく正しい選択肢なんです。
だからこそ私は思うんです。
無理にどちらかを否定する必要はない、と。
お互いに確かな価値をもっている。
これは事実です。
そして一言でまとめるならこうなります。
FF XIVを最高に楽しみたいなら、インテルならCore Ultra 7以上、AMDならRyzen 7 X3D以上を素直に選べばいい。
それが最低限の安心ラインです。
それさえ守れば、後悔することはありません。
私はそう信じていますし、その選択をする方の背中をしっかり押したいと思っています。
これが私の実感であり、社会人としての経験を踏まえた私の結論です。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R67C


| 【ZEFT R67C スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SO


| 【ZEFT R60SO スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61GM


| 【ZEFT R61GM スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R62H


| 【ZEFT R62H スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z44FF


熱いゲーム戦場を支配する、スーパーゲーミングPC。クオリティとパフォーマンスが融合したモデル
頭脳と筋力の調和。Ryzen7とRTX4060のコンビが紡ぎ出す新たなゲーム体験を
静かなる巨塔、Antec P10 FLUX。洗練されたデザインに包まれた静音性と機能美
心臓部は最新Ryzen7。多核で動くパワーが君を未来へと加速させる
| 【ZEFT Z44FF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
BTOと自作、それぞれのFF XIV向け構成の違い
長く使えるだけでなく、自分自身の手で組み上げて調整していく過程が楽しみそのものだと感じたからです。
もちろん、万人にとっての正解ではありません。
人によってはBTOの安心感こそが正義だと思いますし、その考え方を否定する気は一切ないんです。
実際、私自身も仕事が忙しい時期にはBTOに何度も助けられましたし、到着したその日にすぐFF XIVを起動できたときのあの安堵感は忘れられません。
あれは確かに便利でしたよ。
BTOを使っていた頃は、相性問題に頭を悩ませることもなく、BIOSの設定に夜更かしすることもなかった。
そういう意味では時間を金で買っていたんだと思います。
社会人って時間が一番大事じゃないですか。
だからBTOのパソコンを開封して、そのまますぐ使えることは心底ありがたかった。
あのとき私の中で得た感情は「助かった」の一言に尽きますね。
BTOではまず用意されていないパーツの組み合わせを試したところ、結果的に発熱が抑えられ、動作音も静かになった。
それでいてFF XIVの都市部でもフレームレートが安定していたんです。
このとき、思わず声に出したのが「やって良かったなぁ」でした。
自作は楽しいことばかりではない。
パーツが品切れで入荷を何週間も待ったこともあり、価格が急に跳ね上がって悩んだこともありました。
さらにケース選びひとつで数日迷うなんてことはザラです。
最近流行のガラスパネルのピラーレスケースを使ったときもそう。
見栄えは最高でしたが、埃の管理やケーブルの取り回しを考えると、「いやぁ大変だな」と感じる場面だってありました。
それでもね、その試行錯誤がなんだか楽しいんですよ。
気がつけば夜中までパーツをいじっていました。
まるで子どもの頃の工作みたいに。
ストレージやメモリに関しても自由度の高さを実感しました。
BTOだと標準搭載のSSDは容量がそれなりにあっても、速度が物足りないなんてことがよくあるんです。
特にゲームの大型アップデートをインストールするときに「もう少し速ければな」と思ったのを覚えています。
自作なら最初からPCIe Gen4対応のSSDを2TB積んで、後からGen5を増設する余地を残しておくといった工夫ができる。
ここは未来を見越して構成を考える楽しみどころ。
まさに拡張の柔軟さという大きな強みを体感した部分ですね。
冷却の部分でも面白さがあります。
BTOだと空冷や簡易水冷がある程度バランスよく搭載されていて、それは確かに安心なんです。
しかし自作だと、ファンの回転数を調整して静音に寄せてみたり、エアフローを考え抜いたケースを選んでみたり、いろんな試みができるんですよ。
私は毎日のように温度をチェックして、「今日は回転数を落としてみるか」なんて独り言をつぶやく始末。
完全にゲームの一部みたいになっています。
もちろん価格のことはシビアに考えざるを得ません。
無難にまとまったパーツ構成で、そこそこ高性能なマシンが手に入るのは確かです。
ただし、メーカーやこだわりの規格を選びたくなると途端に難しくなる。
そこで自作に手を出せば出すほど費用は跳ね上がるもの。
実際、GPUを最新世代にしたときは正直財布にかなり響きました。
でも完成したPCを前にすると、「高かったけど作って良かった」と思えるんです。
金額以上の愛着が得られるのが自作の醍醐味でしょうね。
必要スペックについても触れないわけにはいきません。
この基準を満たす前提で、BTOにするか自作にするかを決めるのが現実的だと思います。
私の場合は「試行錯誤こそ楽しみ」と思う性分なので自作を選びましたが、忙しい知人には迷わずBTOを薦めました。
だって正直、時間のない人にとってはBTO以上に心強い選択肢はないんですから。
要は立場次第なんですよ。
どちらを選んでもFF XIVは満足して楽しめる。
ただ、自分のこだわりをどれだけ反映させたいかで答えは変わる。
私はきめ細かい設定や将来的な拡張性を追い求めたい気持ちが強いので自作を推しています。
それは単にパソコンを動かすというよりも、「未来への投資」をしている感覚でもあるんです。
BTOは安心と手軽さを買うもの。
自作は手を動かして理想を形にするもの。
両方を経験してきたからこそ、この二つの立ち位置がはっきりと分かります。
SSDはGen4とGen5、体感的に差はあるのか
FF XIVのように頻繁にアップデートがあり、常に大容量データが出入りするオンラインゲームを快適に楽しみたいと思えば、どうしてもストレージの性能が気になるものです。
私自身も実際にGen4からGen5に移行して試してみたのですが、意外なほどゲームプレイそのものの体感は大きく変わりませんでした。
確かにロード時間が2秒ほど短縮される場面はありましたが、それによって戦闘で有利になるとか、ストレスが劇的に減るといった効果までは感じませんでした。
正直、「あれ、こんなものか」と拍子抜けしたのが本音です。
とはいえ、Gen5のSSDは確かに魅力的に映ります。
実測14,000MB/sといった数字を突き付けられると、数字の迫力に心を惹かれてしまうのは人情ですから。
ただしその裏には代償があります。
消費電力が大きくなり、高温になりやすいため、冷却対策を怠るとすぐに性能が落ち込む。
表面的な速さと引き換えに、熱管理という厄介な課題を抱えるわけです。
数字上の魅力だけで飛びつくと、後で後悔する可能性があると思いましたね。
私は手元のBTOパソコンにGen5 SSDを組み込み、FF XIVで試しました。
ログインから都市に入るまでの時間差はGen4と比べてほんの数秒。
ところが動画編集や3Dモデリングの作業では明らかに差が出ました。
数十GBのデータを一気に読み込むとき、読み取りの速さがはっきりわかる。
つまり用途次第で評価は大きく変わるということです。
冷却なしの環境で試した結果も鮮明に覚えています。
真夏の室内温度が30度を超えたとき、数分で書き込み速度が半分まで低下しました。
その瞬間、頭から冷や水を浴びた気分でしたね。
高性能パーツも環境が整わなければ宝の持ち腐れです。
冷却ファンやヒートシンクといった裏方を軽く扱うと、どれほどの性能も輝けない。
これが現実です。
一方でGen4 SSDはどうでしょうか。
例えばファンフェスのように多数のプレイヤーが一斉にログインする状況でも、マップ切替が苛立つほど遅いと感じたことはありませんでした。
コスト面と安定性のバランスを考えると、Gen4は非常に現実的な選択肢です。
ただし容量に関しては要注意です。
FF XIVはアップデートのたびにどんどん膨らみます。
以前私は500GBのSSDを使っていましたが、録画データを保存していたら容量がすぐ限界に達しました。
そのたびに保存場所の整理を強いられ、ゲームを始める前から疲れてしまう。
あの頃はプレイの楽しみよりも片付けの義務感が勝っていた気がします。
今なら最低1TB、余裕を持って2TB以上を選びたいと強く思います。
容量不足が積み重なるストレスは小さな針のように心に刺さり、最終的には意欲までも削ってしまうのです。
私は現実的に考えるとGen4が最も安心して使えると結論づけました。
2TBクラスを積んでしまえば容量不足の心配もなく、冷却に神経を使いすぎる必要もありません。
安心して使える。
余裕のある選択です。
未来を感じさせる技術であるGen5も魅力的ですが、「今、自分が何を求めているのか」を考えれば答えはシンプルです。
ゲームに集中したいだけならGen4で十分。
冷静に考えてみると、最先端の技術を追いかけたくなる気持ちは世代を問わずあると思います。
ですが、実用性とバランスの取れた選択こそが日々の安心につながります。
私は何度もテストを繰り返しましたが、最後に辿り着いた結論は「Gen4で快適に遊ぶこと」。
シンプルで力強い答えです。
安心感。
実際に使える安心感です。
FF XIVを思う存分楽しむなら、コストと冷却の心配が少ないGen4 SSDが間違いのない選択。
心からそう思います。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |